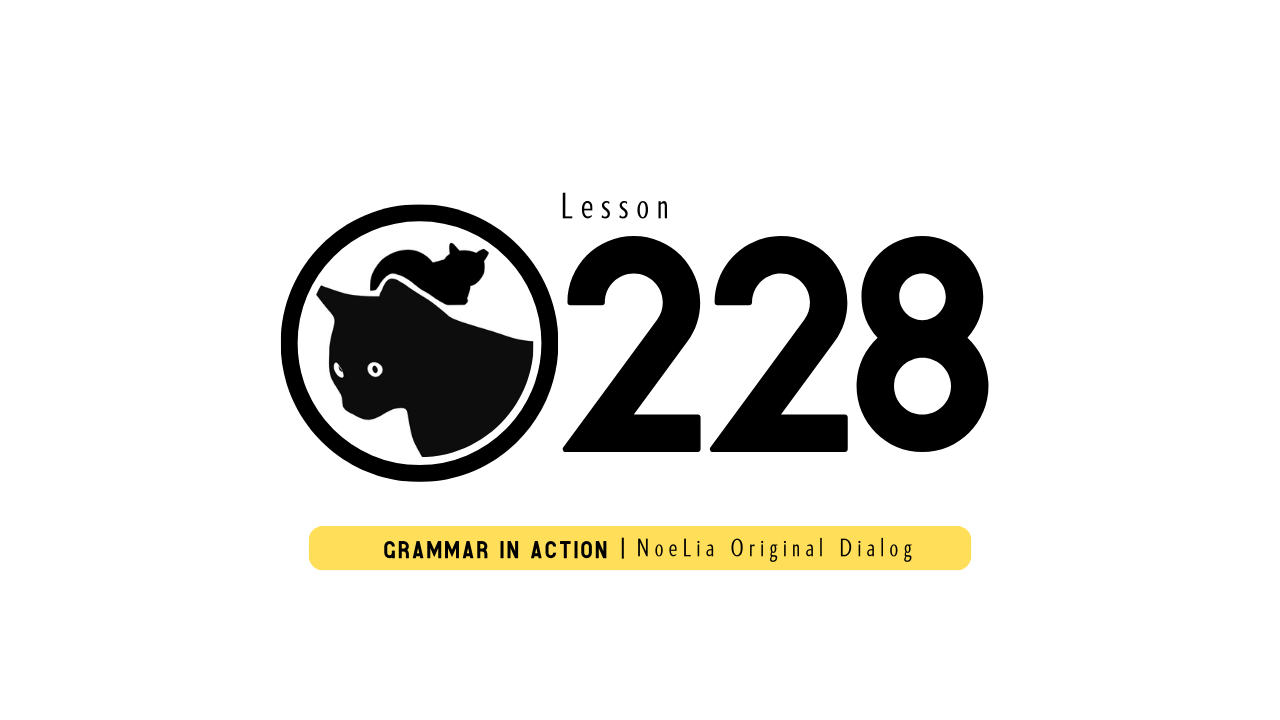👇こちらはLesson 228のコーナー別リンクです
ラジオ英会話 Lesson 228 / 大きなwh語
Grammar and Vocabulary L228 ーNoeLia Original Dialogー
Target Forms L228 / 大きなwh語 ーNoeLia Original Dialogー
Grammar in Action L228 ーNoeLia Original Dialogー
Grammar in Action(ノエリア オリジナル スクリプト)
下記はノエリアオリジナルの解答例です。
ラジオ英会話の『Grammar in Action』コーナーの状況を参考に、そのフレーズを自然に使ったオリジナル会話例も掲載しています!模範解答とは異なる表現を学びつつ、音声を使ってディクテーションや多聴多読に取り組むことで、英語をさらに身近に楽しく学びましょう。実際の会話で活用できる内容が盛り込まれているので、スピーキングの向上や復習にもぜひご活用ください!
NoeLia Answer – 問題1
問題1:オレゴンのどこの出身ですか?私は家族がそこにいます。
引用:「NHKラジオ英会話 2025年3月号」 – 講師:大西泰斗(東洋学園大学教授) – (NHK出版:2025年)
Where in Oregon are you from? I have family there.
問題1:オレゴンのどこの出身ですか?私は家族がそこにいます。
Which part of Oregon are you from? I have family there.
解説: 模範解答は「オレゴンのどこ?」とシンプルに尋ねるのに対し、ノエリアオリジナルの解答例は「どの地域?」と少し柔らかい印象になる。話し手がオレゴンの地理に詳しかったり、州内の特定のエリアを想定している場合に自然に使える。一方で、模範解答のほうが汎用性が高く、一般的な表現として幅広く使える。
Where in Oregon are you from? I have family there.
Where in ~ は「~のどこ?」と特定の地域を尋ねる表現。are you from? は出身地を聞く定番フレーズで、カジュアルでもフォーマルでも使える。I have family there. の there は、話題に出たオレゴンを指している。
Which part of Oregon are you from? I have family there.
Which part of ~ は「どの部分?」というニュアンスがあり、模範解答よりも親しみやすく、具体的なエリアを意識している印象を与える。オレゴンに詳しい場合や、会話の流れである程度エリアが想定されるときに自然に使える表現。
NoeLia Original Dialog
A: I heard you’re from Oregon! Have you always lived there?
B: Yeah, born and raised. I first moved out for college in Seattle, but I still go back to Oregon pretty often—holidays, family gatherings, that kind of thing.
A: Which part of Oregon are you from? I have family there.
B: Oh, cool! I’m from Bend. It’s a great place if you love the outdoors—hiking, skiing, kayaking… basically anything. You should check out Mount Bachelor if you ever visit! Have you been?
A: オレゴン出身なんだって聞いたよ!ずっとオレゴンに住んでたの?
B: うん、生まれも育ちもオレゴン。大学のときに初めて故郷を出てシアトルに住んだけど、ホリデーとか家族の集まりとかで、今でもオレゴンにはちょくちょく帰ってるよ。
A: オレゴンのどこの出身?私、家族がそこにいるんだ。
B: そうなんだ!ベンド出身だよ。アウトドア好きなら最高の場所だよ。ハイキングもスキーもカヤックもなんでもできるしね。もし行くならマウント・バチェラーに行ってみて!行ったことある?
- Have you always lived (there)?: ずっと~に住んでいたの?(「Have you always + 過去分詞」で「ずっと~していたの?」という意味。相手の過去の習慣を確認する表現)
- born and raised: 生まれも育ちも~(「生まれも育ちも同じ場所」を表す定番フレーズ)
- move out: 引っ越す/家を出る(「move」は単体で「引っ越す」という意味だが、「move out」にすると「今まで住んでいた家や地元を離れる」というニュアンスが強くなる。特に、進学や独立で実家を出るときによく使われる。「move」だけだと単に「移動する」「引っ越す」という意味になり、新しい場所への移動にはフォーカスしないが、「move out」は「元の場所を出る」ことを強調する。)
- pretty often: かなり頻繁に(「often」よりも「pretty」を加えることで、「まあまあよく」というニュアンスになる)
- Oh, cool!: へえ、いいね!(カジュアルな相づち。驚きや興味を示すときによく使われる)
- you name it: 何でもあるよ(「you name it」は、「あなたが思いつくものなら何でもあるよ」という意味のカジュアルな表現。リストを挙げた後に「~とか、他にもいろいろ」と付け加えるようなニュアンスになる。直訳すると「あなたが名前を挙げれば、それも含まれる」という意味で、「ハイキング、スキー、カヤック…何でもあるよ」のように、豊富な選択肢を強調するときによく使われる。例えば、「We have sushi, ramen, tempura—you name it.(寿司、ラーメン、天ぷら…何でもあるよ)」のように使う。)
- check out: 試してみる/行ってみる(「out」のコアイメージは「内から外へ」「完全に外へ出る」というもので、「check(確認する)」と組み合わさることで、「確認して、その場を離れる」「見て、実際に試してみる」といった意味になる。そのため、「check out」は単なる情報の確認ではなく、実際に訪れる、試してみるといったニュアンスを持つ表現になっている。)
- Have you been?: 行ったことある?(「Have you been (there)?」の略で、訪問経験を聞くときに自然に使える)
NoeLia Answer – 問題2
問題2:正確にはいつ、あなたは自分の財布がなくなっていることに気づいたのですか?それまでの行動を思い出してみてください。
引用:「NHKラジオ英会話 2025年3月号」 – 講師:大西泰斗(東洋学園大学教授) – (NHK出版:2025年)
Exactly when did you realize your wallet was missing? Retrace your footsteps.
問題2:正確にはいつ、あなたは自分の財布がなくなっていることに気づいたのですか?それまでの行動を思い出してみてください。
When exactly did you notice your wallet was missing? Try to recall everything you did before that.
解説: 模範解答はフォーマルな場面で使われる表現で、警察やホテルスタッフなどの状況に自然に合う。ノエリアオリジナルの解答例は、同じ意味を持ちながら「When exactly」を使うことで、やや口語的で実際の会話の中で自然に響く形になっている。
Exactly when did you realize your wallet was missing? Retrace your footsteps.
「Exactly when」は、特定の瞬間を強調して「正確にはいつ?」と尋ねる表現。「realize」は、状況を理解するという意味を持ち、ここでは「財布がなくなっている状態を認識した瞬間」を指す。「Retrace your footsteps.」は「足取りをたどる」という比喩的な表現で、何をしたか順番に振り返るよう促すフレーズとして使われる。
「When exactly」は「Exactly when」と意味は同じだが、より口語的で柔らかい響きになる。「notice」は、視覚や感覚を通じて気づくことを表し、「realize」よりも、その瞬間の発見に焦点を当てる。「Try to recall everything you did before that.」は、「Retrace your footsteps.」を具体的に説明した形で、過去の行動を思い出すよう指示する表現になっている。
NoeLia Original Dialog
A: Excuse me, I think I lost my wallet somewhere in the hotel. I was just at the lobby café, so it might be there.
B: I understand. When exactly did you notice your wallet was missing? Try to recall everything you did before that.
A: Just now, when I was about to check out. I reached for my wallet, but it wasn’t in my bag. I remember having it when I paid for my coffee earlier.
B: I see. Let me check with housekeeping and the café staff. In the meantime, would you like us to notify security and check the surveillance cameras?
A: すみません、ホテルのどこかで財布をなくしてしまったようです。さっきロビーのカフェにいたので、そこにあるかもしれません。
B: かしこまりました。正確にはいつ、自分の財布がなくなっていることに気づきましたか?それまでの行動を思い出してみてください。
A: ちょうど今、チェックアウトしようとしたときです。財布を取ろうとしたら、カバンの中になかったんです。でも、さっきカフェでコーヒーを払ったときには確かに持っていました。
B: 承知しました。清掃係とカフェのスタッフに確認いたします。その間、警備に連絡して監視カメラを確認させていただきましょうか?
- somewhere in ~: ~のどこかで(場所を特定せずに「どこか」と言いたいときに使う)
- lobby café: ロビーのカフェ(ホテルや空港などの施設内にあるカフェを指す表現)
- so it might be there: だから、そこにあるかもしれません(「might」は可能性を示し、「be there」で場所を示す)
- I understand: かしこまりました(「わかりました」よりも丁寧な表現で、フォーマルな対応時に使われる)
- about to ~: まさに~しようとしていた(直前の動作を表す表現で、「今まさに~しようとした瞬間」に使う)
- reach for ~: ~を取ろうとする(「手を伸ばして取る」という動作を表す)
- but it wasn’t in my bag: でもカバンの中になかった(「wasn’t in ~」は「~に存在しなかった」という言い方)
- I remember having it ~: ~のときに持っていたのを覚えている(「I remember ~ing」で過去の行動を思い出す表現)
- earlier: さっき(「before」と違い、「ほんの少し前」のニュアンスを持つ)
- housekeeping: 清掃係(ホテル業界で使われる用語で、部屋の清掃や忘れ物管理を担当するスタッフ)
- In the meantime: その間に(「while」と同様に「同時に」を意味するが、フォーマルな響きを持つ)
- notify security: 警備に連絡する(「notify」はフォーマルな「知らせる」の表現)
- check the surveillance cameras: 監視カメラを確認する(「surveillance」は「監視」の意味で、警備関連の文脈でよく使われる)
NoeLia Answer – 問題3
問題3:どんな本をあなたは読みますか?私は最近ずっと、たくさん哲学を読んでいます。
引用:「NHKラジオ英会話 2025年3月号」 – 講師:大西泰斗(東洋学園大学教授) – (NHK出版:2025年)
What kind of books do you read? I’ve been reading a lot of philosophy lately.
問題3:どんな本をあなたは読みますか?私は最近ずっと、たくさん哲学を読んでいます。
What types of books do you usually read? Lately, I’ve been really into philosophy.
解説: 模範解答はシンプルに「どんな本を読む?」と尋ねているのに対し、ノエリアオリジナルの解答例は「普段どんな種類の本を読む?」と、読書の習慣や傾向に焦点を当てている。また、「What kind of books」は口語的で日常会話でよく使われる表現なのに対し、「What types of books」はややフォーマルで、ジャンルや分類を意識した聞き方になるため、カジュアルな会話では「kind」のほうが自然なことが多い。後半の表現では、模範解答が「最近たくさん哲学を読んでいる」という行動を伝えているのに対し、ノエリアオリジナルは「最近哲学にハマっている」と、読書に限らず哲学そのものへの強い関心を表現している。
What kind of books do you read? I’ve been reading a lot of philosophy lately.
「What kind of books」は「どんな本?」とカジュアルに尋ねる表現。「do you read?」の現在形は習慣を聞く形で、「I’ve been reading a lot of philosophy lately.」は現在完了進行形を使い、最近ずっと続いている行動を表している。「a lot of」は「たくさんの」という意味で、哲学の本を多く読んでいることを強調している。
What types of books do you usually read? Lately, I’ve been really into philosophy.
「What types of books」は「どんな種類の本?」とややフォーマルな響きがあり、「do you usually read?」を加えることで「普段の読書傾向」を尋ねている。「I’ve been really into philosophy.」は「哲学を読んでいる」よりも「最近哲学にハマっている」と、興味の度合いを強調した表現になっている。
NoeLia Original Dialog
A: Oh, you’re reading Norwegian Wood! I read it too. The writing style is so nostalgic, right? What types of books do you usually read? Lately, I’ve been really into philosophy.
B: Philosophy? Can you eat that? Because if not, I’m not sure I’m interested.
A: Haha, nope. But it does feed your brain. It makes you think about life in ways you never have before.
B: Hmm… so, kind of like mental seasoning? Honestly, even Murakami’s books go right over my head.
A: あ、ノルウェイの森読んでるんだ!私も読んだよ。なんか懐かしい雰囲気の文体だよね。普段どんな本を読むの?最近ずっと、哲学にハマってるんだ。
B: 哲学?それって食べられるの?食べられないなら、興味湧かないんだけど。
A: はは、残念ながら食べられないよ。でも頭の栄養にはなる。今まで考えたこともないようなことを考えさせてくれるんだ。
B: ふーん…つまり、精神的な味付けってこと?うーん、正直俺、村上春樹もちんぷんかんぷんなんだけど。
- writing style: 文体(作家の書き方や表現の特徴)
- nostalgic: 懐かしい(過去を思い出させる感傷的な雰囲気)
- Can you eat that?: それって食べられるの?(冗談めかした言い回し。「興味がない」ことを遠回しに言うフレーズとして使われる)
- feed your brain: 頭の栄養になる(”feed” は本来「食べ物を与える」という意味だが、ここでは「知識を与える」という比喩表現として使われている。Bの「食べられるの?」という冗談に対し、Aが「食べ物ではないけど、知識の栄養にはなる」と返す流れになっている)
- make you think: 考えさせる(「~を深く考えさせる」意味でよく使う)
- in ways you never have before: 今まで考えたこともないような形で(「今までにない方法で」「これまでとは違った角度から」)
- kind of like ~: なんとなく~みたいな感じ(はっきり言い切らず、ふわっとした例えをするときに便利)
- mental seasoning: 精神的な味付け(Bが「哲学って食べられるの?」と冗談を言った流れを受けて、Aの「feed your brain(頭の栄養になる)」という説明に対し、Bがさらに「じゃあ、精神的な味付けみたいなもの?」と例えた表現。「seasoning=調味料」を使い、「哲学は直接食べるものではないけど、考え方にスパイスを加えるもの」と捉えている)
- Murakami’s books: 村上春樹の本(英語では “Murakami” だけで村上春樹を指すのが一般的 だが、日本語では 「村上の本」だけだと不自然 で、村上龍との区別もつかないため、通常 「村上春樹の本」 とフルネームで言うのが普通。英語と日本語での 作家名の省略の仕方に違いがある ため、そのまま訳すと不自然になりやすい。”books” は単なる書籍ではなく「作品」の意味合いも持つ。)
- go over one’s head: 理解を超える/難しくてわからない(「頭の上を飛び越えていく」イメージで、「理解できない」「難しすぎる」といった意味)