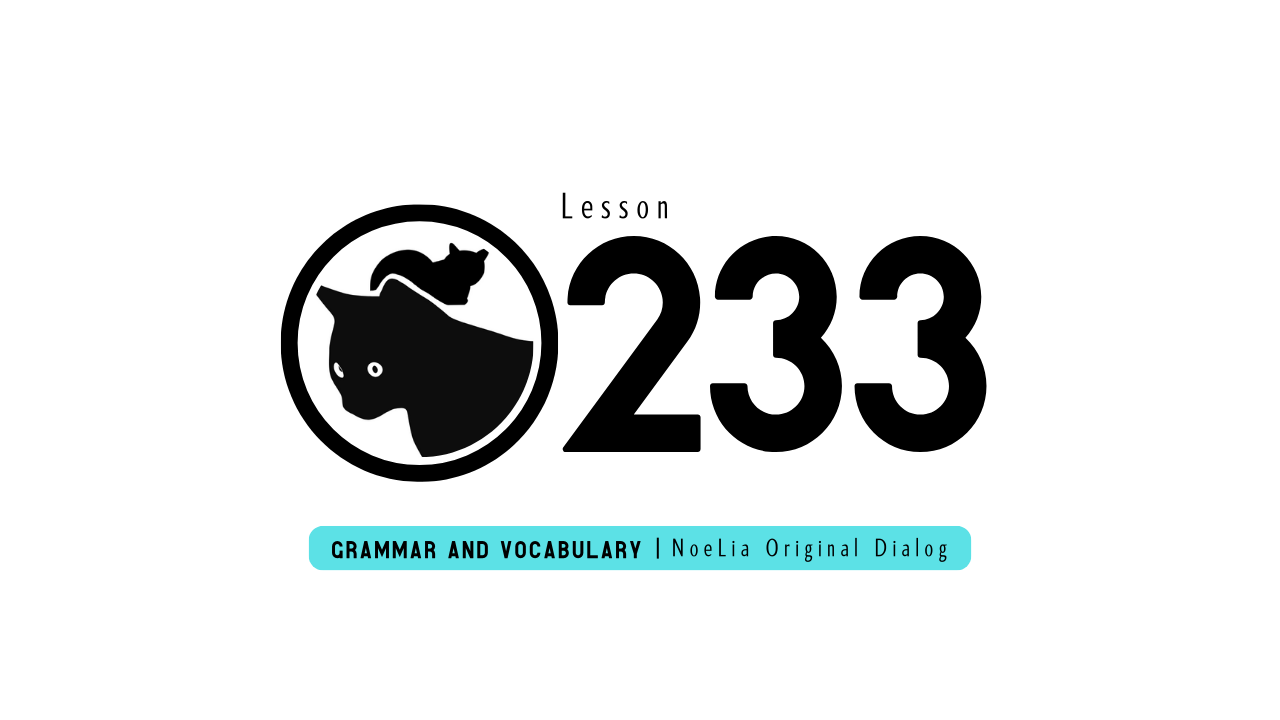👇こちらはLesson 233のコーナー別リンクです
ラジオ英会話 Lesson 233 / 付加疑問文
Grammar and Vocabulary L233 ーNoeLia Original Dialogー
Target Forms L233 / 付加疑問文 ーNoeLia Original Dialogー
Grammar in Action L233 ーNoeLia Original Dialogー
Grammar and Vocabulary(ノエリア オリジナル スクリプト)
下記では、本日の「Grammar and Vocabulary」の学習テーマに基づいた例題とその会話例を掲載しています。
学習内容が実際の会話でどのように活用できるかを具体的にイメージできるよう工夫されており、繰り返し練習することで日常生活でも無理なく使える英語表現を身につけることができます。
また、この素材はリスニングやディクテーション、スピーキングのトレーニングにも最適です。ぜひ学習の定着に役立ててください!
NoeLia Extra Examples – have toの客観
have toの客観
You don’t have to be so formal.
引用:「NHKラジオ英会話 2025年3月号」 – 講師:大西泰斗(東洋学園大学教授) – (NHK出版:2025年)
あなたは、そんなに堅苦しくする必要はありません。
You don’t have to be so self-conscious.
日本語訳: そんなに気にする必要はないよ。
解説: “not have to” で「気にする必要はない」と伝えている。”self-conscious” は「自意識過剰な」「周りの目を気にする」という意味で、緊張している人を安心させる時に使える。
A: Ugh, I hate speaking in front of a crowd. My hands are already shaking, and I haven’t even started yet.
B: You don’t have to be so self-conscious. Just focus on what you want to say. No one is here to judge you.
A: That’s easier said than done. I feel like I’m gonna mess up and completely blank out in the middle of my speech.
B: Even if you do, no one will remember it five minutes later. Seriously, half the audience is probably thinking about lunch already.
A: うわぁ、人前で話すのほんと嫌だ。まだ始まってもないのに、手が震えてる…。
B: そんなに気にしなくていいよ。言いたいことに集中しなって。誰も君のことを評価しようなんて思ってないから。
A: そんなの言うのは簡単だよ…。途中で頭が真っ白になって、大失敗しそうな気がする。
B: たとえそうなったとしても、5分後には誰も覚えてないって。てか、観客の半分はもうランチのこと考えてると思うよ。
- Just focus on ~: ~に集中しなよ(”just” を入れることで「とにかく」「余計なことを考えずに」というニュアンスになる)
- No one is here to judge you.: 誰も君を評価しに来てるわけじゃないよ(”be here to ~” で「~するためにいる」、”judge” は「判断する」「評価する」)
- That’s easier said than done.: 言うのは簡単だけどね(ことわざ的な表現で「やるのは難しい」というニュアンス)
- mess up: 失敗する(カジュアルな言い方で、「台無しにする」「へまをする」という意味)
- blank out: 頭が真っ白になる(”blank” は「空白」という意味の名詞だが、動詞として使われると「(頭が)真っ白になる」「何も考えられなくなる」という意味になる。”out” をつけることで「完全に」「すっかり」のニュアンスが加わる)
- in the middle of ~: ~の途中で(「話の途中で」「作業の途中で」など、中間のタイミングを指す表現)
- Even if you do: たとえそうだとしても(”even if” は「たとえ~でも」という仮定の表現)
- no one will remember it: 誰も覚えてないよ(”will” を使って「未来には気にされない」ことを強調している)
Your apology doesn’t have to be so dramatic.
日本語訳: そんなに大げさに謝らなくてもいいよ。
解説: “not have to” で「そんなに大げさにする必要はない」と伝えている。”dramatic” は「大げさな」「劇的な」という意味で、過剰に反応している人を落ち着かせたい時に使える。
A: Oh no! I’m so sorry! I dropped your coffee, and it got all over your bag… and your jacket!
B: Ugh… okay, that’s annoying, but it’s not the end of the world. A trip to the dry cleaners should fix it. See? The bag’s fine after wiping it down. At least it wasn’t burning hot.
A: Still, I feel awful about it! Let me buy you a new bag or cover the cleaning cost.
B: Your apology doesn’t have to be so dramatic. Just get me another coffee, and we’re good… but make it a large this time.
A: うわっ!ごめん!コーヒーこぼしちゃった…バッグだけじゃなくて、ジャケットにもかかってる…
B: うわ…まあ、確かに面倒だけど、クリーニングに出せばなんとかなるでしょ。ほら、バッグは拭いたらもう分かんないよ。熱々じゃなかったのが救いだね。
A: でも、本当に申し訳ないよ!バッグ買い直すか、クリーニング代出させて!
B: そんなに大げさに謝らなくてもいいよ。コーヒーもう一杯おごってくれたらそれでOK…でも、今度はLサイズでね。
- drop: 落とす(ここでは「コーヒーを落とす」の意味で使われている)
- get all over: ~にべったりつく/~のあちこちにつく(多義語で、文脈によって「汚れや液体が広がる」「人にしつこく干渉する」「誰かにベタベタする」などの意味になる。”all” は「全体」「すべて」を指し、”over” は「広がり」「覆う」イメージを持つため、組み合わせることで「全面に広がる」「あちこちに付着する」ニュアンスが生まれる。ここでは「汚れや液体が広がる」意味で使われている。)
- annoying: うっとうしい/イライラする(「面倒くさい」「わずらわしい」というニュアンスを持つ形容詞)
- it’s not the end of the world: そんなに大ごとじゃない(直訳は「世界の終わりじゃない」、つまり「そこまで深刻なことじゃない」という意味の比喩表現)
- A trip to the dry cleaners should fix it.: クリーニングに出せばなんとかなるよ(”trip to ~” は「~への短い訪問・用事のための外出」を指し、人以外にも使え、物や行動にも適用可能。例えば、”A trip to the mechanic should solve the issue.”(整備工場に持っていけば問題は解決する)や “A trip to the fridge should help.”(冷蔵庫に行けば何かあるかも)などのように使われる。”should fix it” は「直るはず」という予測を表す。)
- wipe down: ふき取る/拭いてきれいにする(”wipe” は「拭く」、”down” をつけることで「しっかり拭く」ニュアンスを強調)
- burning hot: めちゃくちゃ熱い(”burning” は「燃えるような」、”hot” は「熱い」で、組み合わせることで「火傷しそうなほど熱い」という意味になる)
- Still: それでも(「それは分かるけど、それでもやっぱり~」という流れを作る重要な単語)
- cover the cleaning cost: クリーニング代を出す(”cover” は「費用を負担する」という意味で使われている)
- Just get me another coffee: ただコーヒーもう一杯おごって(”just” をつけることで「それくらいでいいよ」と軽く受け流すニュアンス)
- we’re good: もう大丈夫/これでチャラね(”good” を「OK、問題なし」の意味で使っているカジュアルなフレーズ)
- make it a large: Lサイズにしてね(注文時にサイズを指定する時のフレーズ)
NoeLia Extra Examples – 説明ルールはどこにでも4
説明ルールはどこにでも4
It’s the way we’re taught at this school.
引用:「NHKラジオ英会話 2025年3月号」 – 講師:大西泰斗(東洋学園大学教授) – (NHK出版:2025年)
それは、この学校で私たちが教えられている方法です。
It’s the way things are done here.
日本語訳: それが、ここでのやり方なんだ。
解説: the way を使って、「ここで物事がどのように行われるか」を説明している。職場やグループのルールを伝える場面で使える表現。
A: I don’t get it. Why are we doing it this way? We could finish twice as fast if we just used the software.
B: It’s just how we’ve always done it. The manager prefers everything to be double-checked manually.
A: But wouldn’t it be easier to do it differently? I mean, other teams already automated this process.
B: It’s the way things are done here. You’ll get used to it… eventually. Or you’ll just learn to stop questioning it.
A: よく分かんないんだけど。なんでこんなやり方してるの?ソフト使えば、半分の時間で終わるじゃん。
B: 昔からこうやってるからね。マネージャーが全部手作業でダブルチェックするのを好むんだよ。
A: でも、別のやり方の方が簡単じゃない?他のチームはもうこの作業自動化してるし。
B: それが、ここでのやり方なんだ。そのうち慣れるよ…多分ね。もしくは、考えるのをやめるようになるだけかも。
- I don’t get it.: よく分からない。(”get” は「理解する」という意味で、”I don’t get it.” は「理解できない」「納得できない」といったカジュアルな表現。)
- twice as fast: 2倍速く(”twice” は「2倍」、”as fast” は「~と同じくらい速く」という比較表現の一部。”twice as fast” 全体で「標準のスピードの2倍」という意味になり、「2倍速く」や「半分の時間で」というニュアンスを持つ。同様の構造には「twice as much(2倍の量)」「twice as many(2倍の数)」などがある。)
- if we just used ~: もし~を使えば(”just” を入れることで「たったこれだけで」と強調し、簡単な解決策を提示するニュアンスになる。)
- It’s just how we’ve always done it.: 昔からこうやってるからね。(”just” を入れることで「ただ単に」と柔らかいニュアンスを加えている。”have always done” は「ずっとやってきた」という継続の意味を持つ現在完了形。)
- But wouldn’t it be easier to ~?: でも、~する方が簡単じゃない?(”wouldn’t it be” は「~じゃない?」と提案や反論をするときの表現。)
- I mean, ~: つまりさ、~(カジュアルな会話で、自分の意見を補足・強調するときに使う表現。)
- automate: 自動化する(”auto” は「自動」、”mate” は「~化する」の意味を持ち、機械やソフトで手作業を減らすことを指す。業務やシステムの効率化の文脈でよく使われる。)
- You’ll get used to it.: そのうち慣れるよ。(”get used to ~” は「~に慣れる」という意味で、新しい環境やルールについて話す時によく使われる。)
- eventually: いずれは/そのうち(すぐではなく時間が経てばそうなる、という意味を持つ副詞。)
- Or you’ll just learn to stop questioning it.: もしくは、考えるのをやめるようになるだけかもね。(”learn to ~” は「~するようになる」、”stop questioning it” は「疑問を持つのをやめる」という意味で、皮肉っぽいニュアンスがある。)
That’s the way he wants his coffee made.
日本語訳: それが、彼がコーヒーを淹れてほしい方法なんだよ。
解説: “the way” を使って、「彼がどのようにコーヒーを淹れてもらいたいか」を説明している。注文時や好みを伝える場面で使える表現。
A: That’s the way he wants his coffee made. No sugar, extra hot, and a splash of oat milk. Oh, and it has to be in a ceramic cup—he hates paper cups.
B: Sounds specific. Does he complain if it’s not exactly right?
A: Oh, absolutely. Last time, they forgot the oat milk, and he sent it back immediately. And don’t even get me started on the time they gave him a regular lid instead of a sip-through one.
B: Yikes. Remind me never to get his coffee order wrong. Or maybe I’ll just make him get it himself next time.
A: それが、彼がコーヒーを淹れてほしい方法なんだよ。砂糖なし、熱め、オーツミルクを少しだけ。あと、紙コップじゃなくて陶器のカップじゃないとダメらしいよ。
B: ずいぶん細かいね。もしちょっとでも違ったら文句言うの?
A: うん、絶対言うよ。前回オーツミルクを入れ忘れたら、すぐに突き返してし。飲み口付きのフタじゃなくて、普通の蓋を渡された時のことなんて、もう話したくもないわ。
B: うわ…絶対に彼のコーヒー注文ミスりたくないな。てか、もう本人に自分で買いに行かせればいいんじゃない?
- No sugar: 砂糖なし(コーヒーの注文時によく使われる表現。)
- extra hot: 熱め(”extra” は「特に・追加の」という意味を持ち、”extra hot” で「特に熱くして」という注文表現。)
- a splash of ~: ~を少しだけ(”splash” は「はねる」という意味を持つが、飲み物の注文では「ほんの少しの量」というニュアンスで使われる。)
- oat milk: オーツミルク(”oat” は「オート麦」、”milk” は「ミルク」の意味で、オート麦から作られる植物性ミルクのこと。乳製品アレルギーやヴィーガンの人に人気があり、カフェや飲食店のメニューでもよく見かける。)
- ceramic cup: 陶器のカップ(”ceramic” は「陶器の」、”cup” は「カップ」で、紙コップとの違いを表す。)
- hates ~: ~が大嫌い(”hate” は「強く嫌う」という意味の動詞で、日常会話で感情を強く表す際によく使われる。)
- specific: 明確な/具体的な/細かい(「はっきりとした」「特定の」という意味を持ち、要求や説明が細かく、詳細に決められていることを表す。日常会話では「こだわりが強い」「細かい指示」といったニュアンスで使われることが多い。”be specific” で「もっと具体的に言って」というフレーズとしてもよく使われる。)
- if it’s not exactly right: もし少しでも違ったら(”not exactly right” は「完全には合っていない」という意味で、細かいこだわりがある人について話すときに使われる。)
- sent it back: 突き返した(”send back” は「返品する」「送り返す」という意味で、飲食店で注文が間違っていたときの対応として使われる。)
- don’t even get me started on ~: ~についてはもう話したくもない(”get started” は「始める」という意味で、直訳すると「私をその話題について始めさせないで」となる。つまり、「その話を始めたら、文句や不満が止まらなくなるからやめておこう」というニュアンスの表現。何かに対して強い不満やイライラを感じているときに使われ、「~のことを言い出したらキリがない」といった意味に近い。)
- gave him a regular lid instead of a sip-through one: 普通のフタを渡して、飲み口付きのフタじゃなかった(”instead of ~” は「~の代わりに」という意味で、期待していたものと違った場合に使われる。)
- Remind me never to ~: 絶対に~しないように覚えておこう(”remind me” は「私に思い出させて」、”never to ~” は「絶対に~しないように」という意味で、「~は絶対に避けたい」と強調するときに使われる。)
- get his coffee order wrong: 彼のコーヒーの注文を間違える(”get ~ wrong” は「~を間違える」という意味で、注文や指示を誤ったときに使われる。)
- Or maybe I’ll just make him get it himself next time.: てか、もう本人に自分で買いに行かせればいいんじゃない?(”make + 人 + 動詞” は「(人)に~させる」、”next time” は「次回」という意味で、「次はもうやらない」というニュアンスが含まれている。)