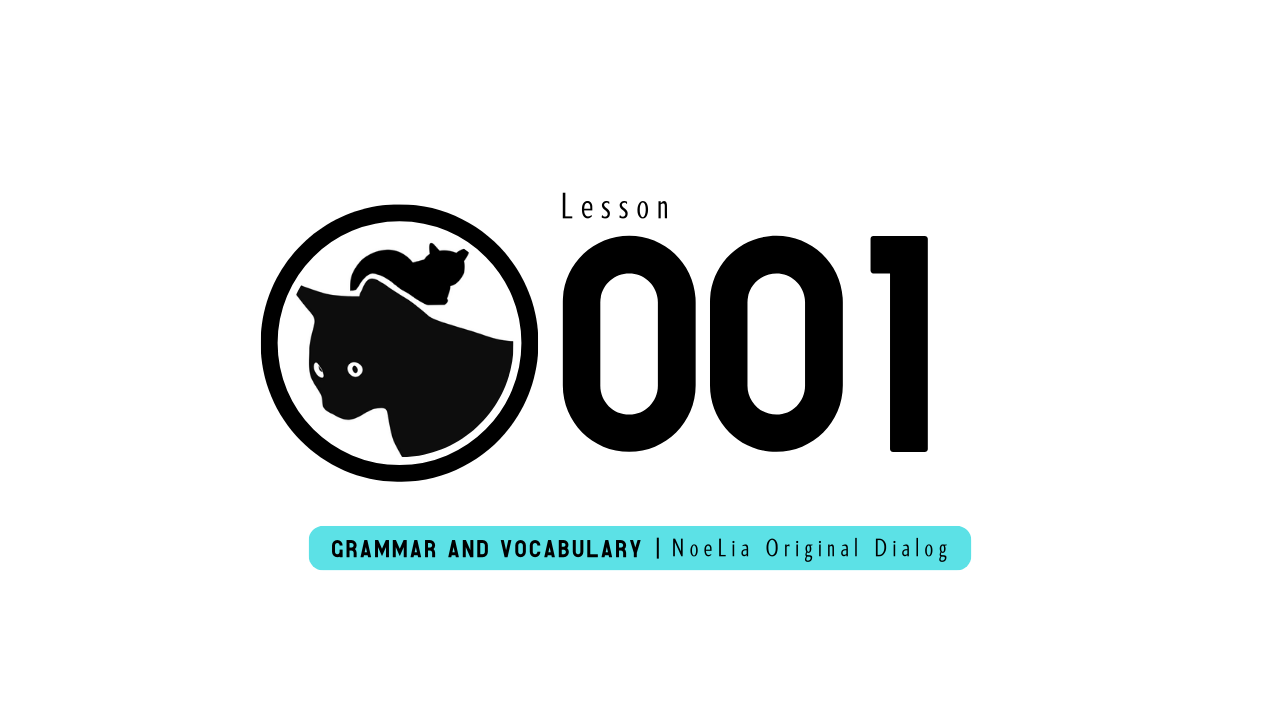👇こちらはLesson 001のコーナー別リンクです
ラジオ英会話 Lesson 001 / 前置詞 about
GRAMMAR AND VOCABULARY L001 ーNoeLia Original Dialogー
GRASP THE CONCEPT L001 / 前置詞 about ーNoeLia Original Dialogー
PRACTICAL USAGE L001 ーNoeLia Original Dialogー
GRAMMAR AND VOCABULARY(ノエリア オリジナル スクリプト)
下記では、本日の「GRAMMAR AND VOCABULARY」の学習テーマに基づいた例題とその会話例を掲載しています。
学習内容が実際の会話でどのように活用できるかを具体的にイメージできるよう工夫されており、繰り返し練習することで日常生活でも無理なく使える英語表現を身につけることができます。
また、この素材はリスニングやディクテーション、スピーキングのトレーニングにも最適です。ぜひ学習の定着に役立ててください!
NoeLia Extra Examples – wh節
wh節
That’s what the sign says.
引用:「NHKラジオ英会話 2025年4月号」 – 講師:大西泰斗(東洋学園大学教授) – (NHK出版:2025年)
それが、その看板が言っていることです。
That’s how he pulled it off.
日本語訳: 彼はそうやってやってのけたんだよ
解説: “how he pulled it off” は wh節 で、「どうやってうまくやったか(ということ)」を示しています。疑問文の語順ではなく、事実として述べられている点に注意。”pull it off” は「やってのける」「うまくやる」という意味の口語的表現です。直訳すると「それを引っ張って成功させる」となりますが、難しいことを見事に成し遂げた時に使われるカジュアルなフレーズです。
A: I still can’t believe he managed to win the prefectural speech contest. I was sure Ayaka had it in the bag after that mock round.
B: He recorded himself every day and worked with Mr. Saito, the debate coach, for weeks. That’s how he pulled it off.
A: Oh, so he actually worked on things like pacing and intonation?
B: Yeah, and he even memorized the entire script word for word—he knew exactly when to pause and how to land each line.
A: あの県のスピーチコンテストで彼が優勝したなんて、今でも信じられないよ。模擬ラウンドの時点では、アヤカが間違いなく本命だと思ってたのに。
B: 彼、毎日自分の声を録音して、何週間も齋藤先生(ディベート部のコーチ)と練習してたんだよ。そうやってやってのけたんだ。
A: へえ、話すスピードとかイントネーションもちゃんと練習してたってこと?
B: うん、スクリプトは丸暗記してたし、「どこで間を取るか」「どう言い切るか」まで全部計算してたってさ。
- can’t believe: 信じられない(感情・驚きを表す非常に日常的なフレーズ。「本当に〜なの!?」というニュアンスでよく使われる)
- manage to do: なんとか〜する(“manage” は「管理する」よりも「困難を乗り越えて達成する」という意味で使われることが多く、ここでは「やり遂げた」感を強調)
- have it in the bag: 勝ったも同然だと思う(直訳は「袋の中にある」=「もう確実に手に入れた」という意味のイディオム。試合・コンテスト・選挙など、何かに勝つ・成功することがほぼ確実だと思っているときに使う。日常会話でもよく聞かれる表現で、特に友人同士の会話、学校や職場の雑談などで頻出)
- record oneself: 自分自身を録音/録画する(record は「録音する」「録画する」の両方の意味を持つ動詞で、oneself を目的語にすると「自分の声や映像を録る」という意味になる。英語のスピーチ練習・プレゼン準備・発音チェック・動画投稿など、幅広い場面で使える表現)
- work with: 〜と一緒に取り組む(協力・指導の場面でよく使う組み合わせ。学習やプロジェクトなど、幅広い場面で使える)
- coach: コーチ/指導者(スポーツに限らず、スピーチやディベートなどの指導者にも使える語)
- pull it off: やってのける/うまくやる(直訳は「それを引っ張って成功させる」。難しいことを見事に成し遂げたときに使うカジュアルな表現)
- work on: 〜に取り組む(スキルの向上や改善を目指して努力するという意味で、会話でも頻出)
- pacing: 話すスピードの調整(“pace” は「歩く速度」などの意味だが、スピーチでは「話すテンポ」としてよく使われる)
- intonation: 抑揚/イントネーション(英語のリズムや強弱に関わる重要な発音要素。スピーチだけでなく日常会話でも重要)
- memorize: 暗記する(日本の学習者には馴染み深いが、日常会話では “remember” と混同されやすいので使い分けに注意)
- word for word: 一語一句そのままに(直訳的に「単語ごとに」だが、比喩的に「完全に同じ内容で」覚える・言うという意味でよく使われる)
That’s when the whole thing fell apart.
日本語訳: すべてが崩れ始めたのはそのときだよ。
解説: when the whole thing fell apart が wh節で、「いつ物事が崩れたのか(ということ)」を意味します。wh語の後ろが平叙文の形になっている点が wh疑問文との違いです。
A: We were doing great in the qualifiers—three wins in a row, and Takuya hit a home run in every game.
B: I remember! He was totally on fire that week.
A: That’s when the whole thing fell apart—he pulled a muscle during practice right before the finals.
B: Oh man… losing your cleanup hitter at the worst time? That must’ve shaken the whole team.
A: 予選では絶好調だったんだよ。3連勝で、タクヤは毎試合ホームラン打ってたし。
B: 覚えてるよ!あの週のタクヤ、マジでノリに乗ってたよね。
A: でも、すべてが崩れ始めたのはそこから。決勝の直前に、練習中に筋肉痛めちゃってさ。
B: うわ…4番打者をあんなタイミングで失うなんて、そりゃチームも動揺するよね。
- do great: 絶好調である(“do” は「する」だけでなく「うまくやる」「成功する」という意味でも使われる。スポーツや仕事で成果を出しているときによく使われるフレーズ)
- qualifier: 予選(スポーツなどの大会で「本戦に進む前の予選」を指す。高校生スポーツの文脈では頻出)
- in a row: 連続で(”row” は「一列に並んだ状態」がコアイメージ。そこから「出来事が一列に並ぶ」=「連続して起こる」ことを意味するようになった。たとえば “three wins in a row” は「3連勝」、”five days in a row” は「5日連続で」という意味になる)
- hit a home run: ホームランを打つ(野球の動作表現だが、比喩的に「大成功を収める」としても使われる)
- remember: 覚えている(見落とされがちだが、「思い出す」だけでなく、「記憶している」状態も表す動詞)
- be on fire: 絶好調である(直訳は「燃えている」だが、比喩的に「勢いがある」「活躍している」状態を表すカジュアルな表現)
- fall apart: 崩れる/バラバラになる(”fall” は「落ちる・崩れる」、”apart” は「離れた状態」がコアイメージ。組み合わさることで、「一つだったものがバラバラに崩れる」ニュアンスになる。物理的なモノだけでなく、チーム、計画、人間関係などが壊れる場面でもよく使われる)
- pull a muscle: 筋肉を痛める(“pull” は「引っ張る」だが、ここでは筋肉を「伸ばして痛める」という意味で使われる)
- right before: ~の直前に(“just before” より少し柔らかい表現で、会話では非常によく使われる時間のつなぎ言葉)
- Oh man: うわ〜/マジか(驚きや落胆を表すカジュアルな間投詞。若者の日常会話で頻出)
- cleanup hitter: 4番打者(”clean up” は「一掃する」がコアイメージで、塁上のランナーを一気に返す役割を担う打順。英語では4番バッターを指すのが一般的だが、日本語の「クリーンアップ」は3~5番全体を指すこともある)
- at the worst time: 最悪のタイミングで(“at the best time” の逆。トラブルやアクシデントが「今!?」という時に使う)
- shake the team: チームに衝撃を与える(“shake” は「振る」だけでなく、比喩的に「動揺させる」「感情を揺さぶる」という意味でも使われる)
NoeLia Extra Examples – 単語の相性のよさ
単語の相性のよさ
I want to know about my career.
引用:「NHKラジオ英会話 2025年4月号」 – 講師:大西泰斗(東洋学園大学教授) – (NHK出版:2025年)
私は、私のキャリアについて知りたいと思っています。
We can’t afford to lose this chance.
日本語訳: このチャンスは逃せないよ。
解説: afford は「〜する余裕がある(ない)」という意味で、「to の先にある行動ができるかどうかのライン」を意識させる動詞と自然に結びついています。
A: I’m thinking of submitting my app design from the grad exhibition to the National Design Awards. I refined the user flow and visuals, but I’m still not sure if it checks all the judging criteria.
B: You totally should! That concept for the mindfulness tracker? It’s clean, intuitive, and honestly way more polished than half of what made it to the finals last year.
A: I don’t know… What if they think it lacks originality or depth?
B: We can’t afford to lose this chance. Even Ms. Takeda said your use of color theory and accessibility features was professional-level.
A: 大学院の展示会に出したアプリのデザイン、ナショナルデザインアワードに応募しようか迷ってるんだよね。ユーザーフローとビジュアルは改良したんだけど、審査基準を全部満たしてるかまだ自信がなくて。
B: 絶対応募すべきだよ!あのマインドフルネストラッカーのコンセプト、すごく洗練されてて直感的だし、正直、去年の最終選考に残ったものより全然出来がいいよ。
A: うーん、どうかな…独創性とか深みに欠けるって思われたらどうしよう。
B: せっかくのチャンス、逃すわけにはいかないよ。武田先生も、君の色彩理論の応用とアクセシビリティ機能はプロレベルだって言ってたじゃん。
- submit: 提出する(フォーマルな文脈でよく使われる動詞で、コンテストや書類、論文などに「応募する」「提出する」という意味)
- grad exhibition: 卒業制作展(”grad” は “graduate” の略。アートやデザイン系の学校で行われる展示会)
- refine: 改良する/磨きをかける(「細かい部分まで手を加えて、より良くする」という意味。デザインや文章に対して使われることが多い)
- user flow: ユーザー導線(アプリやウェブサービスにおける、ユーザーが画面をどう移動するかの流れを表す専門用語)
- visuals: ビジュアル/視覚要素(デザインの見た目やレイアウトなど、視覚的に訴える要素全般を指す)
- check (criteria): 満たす/合っているか確認する(ここでは「基準をクリアしているか」の意味で、“check” を「調べる」ではなく「合格ラインに達しているか」の感覚で使っている)
- judging criteria: 審査基準(コンテストなどで用いられる評価ポイント。複数の視点で構成される)
- You totally should!: 絶対応募すべき!(カジュアルで親しい場面で使われる励まし表現。「絶対やるべきだよ!」のニュアンス)
- mindfulness tracker: マインドフルネスの記録アプリ(”mindfulness” は「今この瞬間に意識を向ける心の状態」、”tracker” は日々の活動を記録するツールを意味する)
- intuitive: 直感的に使いやすい(ユーザーが説明なしでも自然に操作できるという意味で、UX/UIの文脈でよく使われる)
- polished: 洗練された/完成度が高い(本来は「磨かれた」という意味だが、デザインや発表内容などが「手をかけて仕上げられている」という比喩表現として使われる)
- make it to: ~に到達する(”make it to the finals” は「最終選考に残る」という意味の決まり文句)
- lack (originality or depth): ~が欠けている(”lack” は「不足している」「欠如している」という意味で、コンセプトやアイデアに対して使われることが多い)
- color theory: 色彩理論(デザインやアートで用いられる「色の組み合わせや印象」に関する理論)
- accessibility features: アクセシビリティ機能(視覚や身体にハンディのある人でも使いやすくするための配慮や機能。デザイン評価の大事な要素)
- professional-level: プロ並みのレベル(”at a professional level” の短縮表現。作品やスキルのレベルがプロと同等であることを示す)
He pretends to know everything.
日本語訳: 彼、なんでも知ってるふりをするんだよね。
解説: pretend は「〜のふりをする」という意味で、to の先にある“演じている行動”とのコンビネーションが自然です。
A: I tried correcting him about the project timeline in the shared doc, but he brushed it off like I was overreacting.
B: That sounds just like him. He hates being told he’s wrong—even when he clearly is.
A: It’s like he doesn’t even listen during meetings. He just talks over people and assumes he’s right.
B: He pretends to know everything. That’s the real issue—it shuts down the whole team dynamic.
A: プロジェクトのスケジュールが違うって、共有ドキュメント上で修正入れたんだけど、僕が大げさに反応してるみたいな感じで流されちゃってさ。
B: ああ、いかにも彼っぽいね。間違ってても、人から指摘されるのが本当に嫌なんだよ。
A: 会議中も、まるで人の話聞いてないしさ。ひたすら被せるように話して、自分が正しいって決めつけてる感じ。
B: 彼、なんでも知ってるふりをするんだよね。それが一番の問題。チームの空気すら壊しちゃってるよ。
- correct (someone): (人の間違いを)訂正する(ここでは “correct” が動詞として使われており、「修正する」というよりも「間違いを指摘して正す」という意味で用いられている)
- shared doc: 共有ドキュメント(“doc” は “document” の略で、Google Docs などを指すことが多い。チーム作業や共同編集で頻出の表現)
- brush off: 軽くあしらう/取り合わない(“brush” は「軽く払う・こする」がコアイメージで、ブラッシュアップ(brush up)と同じ語源。ただし意味はまったく異なり、ここでは「相手の言葉や提案を払うように無視する・受け流す」ことを指す。カジュアルで少し冷たい響きのある表現)
- overreacting: 過剰に反応すること(“react” に “over” を加えることで「過剰に反応する」という意味になり、感情の動きを表す語としてよく使われる)
- That sounds just like (him): いかにも彼らしいね(“That sounds like…” は人の特徴的な行動に対して使う言い回しで、「まさに○○っぽい」と共感や皮肉を込めて使われる)
- hate being told (he’s wrong): 間違いを指摘されるのが嫌い(“hate” は「〜するのが嫌い」、その後ろに受動態の “being told” を取る構文がポイント)
- talk over (people): 人の話にかぶせて話す(相手の発言中に話し始めることで、無視したり遮ったりすることを意味するカジュアルな表現)
- assume (he’s right): 自分が正しいと思い込む(“assume” は「思い込む」「決めつける」の意味で、人の態度や考えを指す際によく使われる)
- That’s the real issue: それが本当の問題だ(“That’s the issue” に “real” を加えることで「根本的な問題である」という意味を強調)
- shut down (a dynamic): 雰囲気ややりとりを壊す/止めてしまう(“shut down” は「止める」「閉じる」などの意味で、ここでは「チームのやりとりを壊す」比喩表現として使われている)
- team dynamic: チームの空気/人間関係の流れ(“dynamic” のコアイメージは「変化し続けるエネルギーの流れ」や「力の相互作用」。ここでは、メンバー同士の関係やコミュニケーションがどのように影響し合って動いているか、という意味で使われる。※日本語の「ダイナミック」は「迫力がある・力強い」という意味で使われることが多いが、英語の “dynamic” は「常に変化している」「流動的な関係性」といったニュアンスが強く、静的ではない状態を表す)