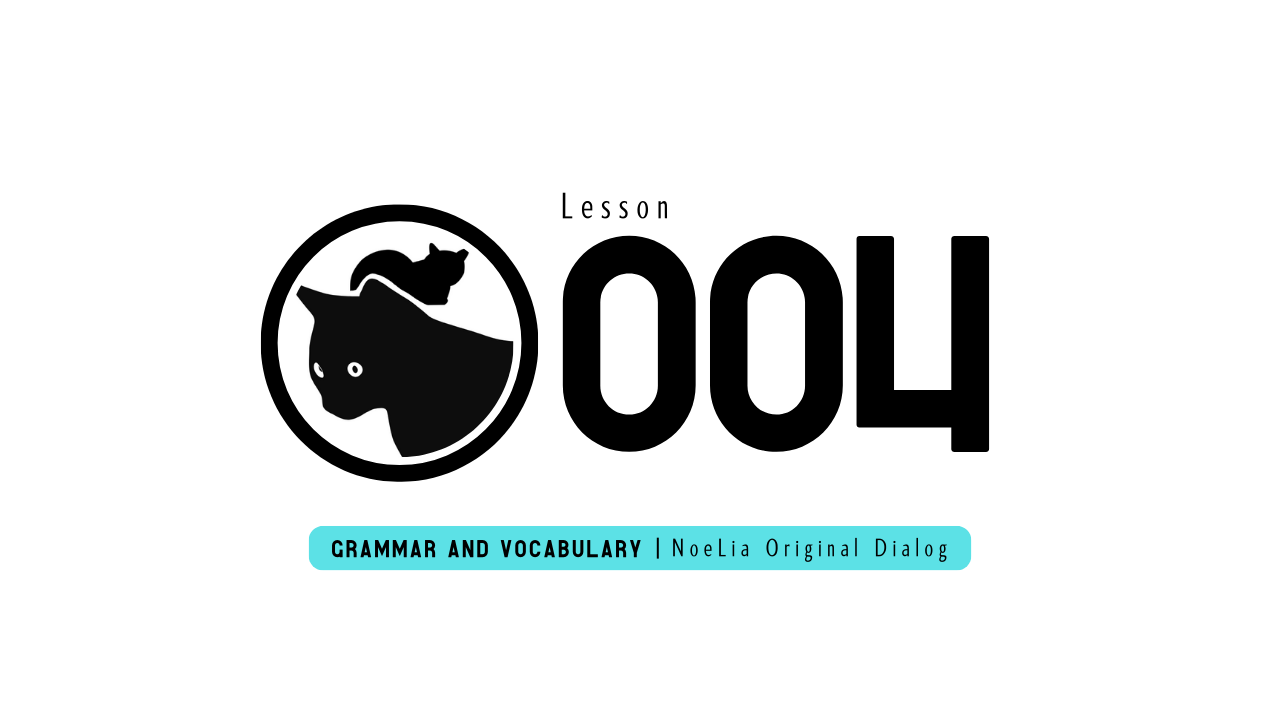👇こちらはLesson 004のコーナー別リンクです
ラジオ英会話 Lesson 004 / 前置詞 on ③ーステージ
GRAMMAR AND VOCABULARY L004 ーNoeLia Original Dialogー
GRASP THE CONCEPT L004 / 前置詞 on ③ーステージ ーNoeLia Original Dialogー
PRACTICAL USAGE L004 ーNoeLia Original Dialogー
GRAMMAR AND VOCABULARY(ノエリア オリジナル スクリプト)
下記では、本日の「Grammar and Vocabulary」の学習テーマに基づいた例題とその会話例を掲載しています。
学習内容が実際の会話でどのように活用できるかを具体的にイメージできるよう工夫されており、繰り返し練習することで日常生活でも無理なく使える英語表現を身につけることができます。
また、この素材はリスニングやディクテーション、スピーキングのトレーニングにも最適です。ぜひ学習の定着に役立ててください!
NoeLia Extra Examples – wh疑問文の3点セット
wh疑問文の3点セット
What are you doing in Australia?
引用:「NHKラジオ英会話 2025年4月号」 – 講師:大西泰斗(東洋学園大学教授) – (NHK出版:2025年)
あなたはオーストラリアで何をしているのですか?
What are we missing here?
日本語訳: これ、私たち何か見落としてる?
解説: missing の後ろが空所で、what がそれを尋ねています。are が主語 we の前に来て疑問形になっています。
A: Flights are booked and the hotel in London’s confirmed—right near Covent Garden, just like we planned.
B: Perfect. I also booked us tickets for the West End shows and the British Museum’s special exhibit on ancient scripts.
A: What are we missing here?
B: Travel insurance. If one of us loses our luggage or needs medical help, we’ll be glad we sorted it out in advance.
A: 飛行機のチケットは取ったし、ロンドンのホテルも予約済み。コヴェント・ガーデンのすぐそばで、計画通りだよ。
B: ばっちりだね。ウエストエンドのショーと、大英博物館の古代文字の特別展示もチケット取っておいたよ。
A: 他に何か見落としてない?
B: 旅行保険かな。荷物をなくしたり、医療が必要になった時のために、事前に準備しておいた方が安心だよ。
- book (flights/hotel): (飛行機やホテルを)予約する(「book」は「本」以外にも「予約する」という意味があり、旅行の文脈で非常によく使われる動詞)
- confirmed: 確定済み(「confirm」は本来「確認する」「確証を与える」という意味だが、ホテルや予約などの場面では「予約内容が正式に認められた/確定した」というニュアンスで使われる。受け身の形 “is confirmed” は「〜が確認された → もう変更の余地がない」という状態を自然に表すため、日常会話でも頻出)
- right near: すぐ近くに(「right」は「正確に、まさに」という強調の意味。場所をより明確に指す表現)
- just like we planned: 計画通りに(”just like” で「まさに〜のように」。ネイティブがよく使うカジュアルな比較表現)
- Perfect: ばっちり/完璧(短く一言で「いいね!」と返すときの自然なリアクション)
- tend to get: 〜になりがち(”tend to” は「〜しがち」という性質を表す表現。ここでは「満席になりやすい」)
- fully booked: 満席/満員(「book」が受け身で使われている形。「完全に予約が埋まった」という意味)
- insurance: 保険(旅行や医療など、日常生活で重要なトピック。学習語彙としても必須)
- get sick: 体調を崩す/病気になる(非常に基本的だが、会話でよく使う動作表現)
- go wrong: うまくいかなくなる/問題が起きる(「wrong」は本来形容詞だが、「go wrong」では副詞的に使われ、「物事が悪い方向に進む」という結果の状態を表している。“go+形容詞”の形で「~な状態になる」という構造の中で、「go wrong」は「状況が悪くなる」「何かが問題になる」という意味で非常によく使われる定番表現)
- we’ll be glad we sorted it out: 手配しておいてよかったと思うだろう(”sort out” は「整理する/処理する/解決する」という動詞句で、ネイティブが非常によく使う)
- in advance: 事前に(準備や計画の文脈で頻出する副詞句)
Who are you texting at this hour?
日本語訳: こんな時間に誰にメッセージしてるの?
解説: texting の後ろが空所で、who がその相手(人)を尋ねています。are you の語順で疑問文を作っています。
A: You seem a bit distracted tonight. You haven’t even taken a sip of your chamomile.
B: Huh? Oh, sorry. I’ve been replying to some messages—kind of lost track of time.
A: Who are you texting at this hour? It’s nearly midnight, and you look worried.
B: My college roommate, Josh. He just messaged me that his dad had a stroke, and he’s completely alone at the hospital in Cincinnati. I didn’t want to leave him hanging.
A: 今夜ちょっと上の空じゃない?カモミールティー、一口も飲んでないよ。
B: え?ああ、ごめん。ちょっとメッセージ返してたの、時間忘れてた。
A: こんな時間に誰にメッセージしてるの?もう真夜中だし、ちょっと心配そうだよ。
B: 大学時代のルームメイト、ジョシュ。さっき連絡があって、お父さんが脳卒中で倒れたらしいの。シンシナティの病院に一人きりでいて…放っておけなくて。
- seem a bit distracted: 少し上の空のようだ(”seem” は「~のように見える」、”distracted” は「気が散っている」状態を表す。日常会話で相手の様子を気づかう時によく使う組み合わせ)
- take a sip: 一口飲む(”sip” は「少量をすする・飲む」の意味。熱い飲み物やハーブティーなどを飲むときに自然な表現)
- lost track of time: 時間を忘れていた(”track” は「記録・経過」、”lose track of ~” で「~を見失う」「把握できなくなる」。ここでは「時間の経過に気づかなかった」意味)
- at this hour: こんな時間に(直訳は「この時間に」。夜遅くや早朝など、普通は連絡しない時間帯を指して使われることが多い)
- had a stroke: 脳卒中を起こした(”stroke” のコアイメージは「一撃・ひと振り・滑らかな動き」。たとえば「ゴルフの一打」「筆のひと書き」「なでる動作」などがある。もともと “stroke” は動詞 “strike(打つ、衝突する)” の過去分詞形として使われていた歴史があり、どちらも「何かが突然当たる・衝撃がある」という感覚を持つ。
医療用語では、その衝撃が脳を襲う突然の一撃のようなイメージにつながり、「脳卒中(=脳への打撃)」を表すようになった) - leave someone hanging: 誰かを宙ぶらりんにする(”hang” は「吊るす」。返事や対応をせずに放っておくニュアンスがあり、「連絡を待たせる」「気にかけないままにする」という意味で使われる口語表現)
NoeLia Extra Examples – 主語を尋ねるwh疑問文
主語を尋ねるwh疑問文
Who said my name?
引用:「NHKラジオ英会話 2025年4月号」 – 講師:大西泰斗(東洋学園大学教授) – (NHK出版:2025年)
誰が私の名前を言ったのですか?
What ruined the mood?
日本語訳: 何がその場の雰囲気を台無しにしたの?
解説: この文は主語を尋ねる疑問文で、wh語(what)が主語の位置に入り、語順は平叙文と同じ。助動詞は不要で、「何が雰囲気を壊したのか?」と原因を尋ねる自然な言い方。
A: I noticed things got kind of awkward after your speech at James’s party.
B: I was trying to lighten the mood, but I guess saying that turning 30 is “basically the start of the downhill slide” didn’t land well.
A: What ruined the mood? Do you think it was that line, or the way you winked at him afterward?
B: Probably both. He’s been touchy about his age since his last birthday—it was a bit tone-deaf on my part.
A: ジェームズの誕生日会でのスピーチのあと、ちょっと気まずい雰囲気になった気がしたんだけど。
B: 場を和ませようと思ったんだけど、「30歳ってほぼ人生の下り坂の始まり」って言ったのがウケなかったかもな。
A: 何が雰囲気を壊しちゃったんだろうね?あのセリフのせいかな、それともその後にウィンクしたのがいけなかったのかな?
B: たぶん両方だな。あいつ、前の誕生日あたりから年齢のこと気にしてるし…ちょっと無神経だったかも。
- notice: 気づく(”notice” は、目に見えるものや雰囲気の変化に対して「ん?なんか変だな」と思うときに使う。「see(見る)」や「realize(はっきり理解する)」よりも感覚的で、その場の空気や人の様子の“ちょっとした変化”に気づく感じ。「気づいた」って日本語にすると少しかたく聞こえる場面もあり、実際の会話では「そう思ったんだよね」とか「なんか変だったよね」みたいな“ちょっと引いた感想”に近いニュアンスで使われることが多い。だから文脈によっては「感じた」「思った」って訳す方が自然になることもよくある)
- awkward: 気まずい(人間関係や場の雰囲気に対して「ぎこちない」「居心地が悪い」などの意味でよく使われる)
- lighten the mood: 雰囲気を和らげる(”lighten” は「軽くする」という意味。気まずさや緊張を「和らげる」ときによく使われる)
- turning 30: 30歳になること(”turn” は年齢の節目を表すときに使われる基本動詞。例:”He just turned 18.”)
- the start of the downhill slide: 下り坂の始まり(比喩的表現。”downhill” はもともと「坂を下る」意味だが、人生や状況が「悪くなっていく」ときにも使われる)
- didn’t land well: うまく伝わらなかった/ウケなかった(”land” は本来「着地する」「届く」といった動きを表す動詞。飛行機が地面に着地するように、ある言葉や行動が相手に“届く”ことを比喩的に表している。そこから転じて、ジョークや発言、アイディアなどが「相手にうまく伝わる」「狙った反応を得られる」状態を “land well” と言い、逆にうまく伝わらず微妙な空気になった時は “didn’t land well” と表現する。ネイティブが日常会話でよく使う自然な言い回し)
- that line: あのセリフ(”line” は「台詞」や「発言」の意味。映画や会話などの決まり文句にも使える)
- winked at him: 彼にウィンクした(”wink” は「ウィンクする」という動作動詞。相手に特別な意図やジョークを伝える時に使われやすい)
- probably both: たぶん両方(”probably” は「おそらく」。”both” を強調して「どっちも」が原因だったことを示すカジュアルな返答)
- touchy about ~: ~に対して敏感になっている(”touchy” は「デリケートな」「怒りっぽい」という意味を持つ形容詞。”be touchy about 〇〇” で「〇〇を気にしている/言われたくない」といった状態を表す。”touchy” は動詞 “touch(触れる)” から派生していて、「ちょっとでも触れられると反応してしまう=すぐに感情が動く・怒る・気にする」といったイメージ。たとえば年齢、体型、成績など、触れられたくない話題に対して使われることが多い)
- tone-deaf: 空気が読めない/場の雰囲気に鈍感な(本来は「音痴」という意味だが、会話では「場の雰囲気が読めない」という比喩でよく使われる)
Who called the shots back then?
日本語訳: あのとき指揮を取っていたのは誰?
解説: この文は主語を尋ねる疑問文で、wh語(who)が主語の位置にそのまま入り、語順は平叙文と同じ。助動詞は不要で、「あのとき誰が実際に仕切っていたのか?」を尋ねる自然な言い回し。口語では「誰が決定権を握ってたの?」という意味でよく使われる表現です。
A: That logistics project we did for the Osaka branch three years ago—it was absolute chaos from day one.
B: Who called the shots back then? I remember hearing there were way too many conflicting instructions.
A: Technically, it was Mr. Tanaka on paper, but honestly, it felt like Keiko from sales was quietly running the show behind the scenes.
B: Yeah, that sounds like her. She’s the kind who doesn’t wait around for approval—she just makes things happen.
A: 3年前に大阪支社向けにやったあのロジスティクスのプロジェクトさ、最初からもうめちゃくちゃだったんだよ。
B: あのとき指揮してたのって誰だったの?指示がバラバラだったって聞いたけど。
A: 一応書類上は田中部長だったけど、実際には営業の恵子さんが裏で全部仕切ってた感じだったな。
B: ああ、彼女ならありえる。承認を待たずにどんどん物事を動かすタイプだもんね。
- project: プロジェクト(仕事や課題などのまとまった取り組みのこと。英語では「大きくて特別なもの」だけでなく、もっとカジュアルに「何かに取り組んでること全般」を表すときにもよく使われる。日本語で「プロジェクト」というと少しかたい印象があるけど、英語では「うちのチームで今やってるやつ」とか「新しい試み」くらいの感覚で気軽に使うことが多い)
- logistics: 物流/ロジスティクス(物資や情報を効率よく動かすしくみ。企業活動の一部として頻出)
- absolute chaos: 完全な混乱(”absolute” は「完全な・絶対的な」という意味の形容詞で、”absolutely” という副詞には馴染みがあっても、形容詞の “absolute” は日常会話では見慣れない人も多い。”absolute chaos” という組み合わせで「どうしようもないほどの大混乱」「制御不能なごちゃごちゃ」といった強いインパクトを与える表現になる。類義語として “complete chaos” や “total chaos” もあるが、”absolute” はそれらよりやや堅く響くぶん、強さ・極端さが際立つ)
- from day one: 初日から/最初から(”day one” は比喩的に「始まりの日」。トラブルや成功のスタートを語るときに使う)
- called the shots: 指揮を取った/主導権を握った(”call the shots” は「誰が何をするかを決める=仕切る」という意味のイディオム。もともとは軍隊で射撃のタイミングを命じる指揮官の役割に由来し、そこから転じて「グループや状況をコントロールする人」「最終決定権を持つ人」を表す。会話では「誰が実際に決めてたの?」という流れでよく登場し、上司・リーダーだけでなく、裏で仕切ってる人にも使えるのがポイント)
- I remember hearing: ~って聞いた覚えがある(”remember” + 動名詞で「〜したことを覚えている」。”hear” は「聞く」だがここでは「耳にした」の意)
- conflicting instructions: 矛盾する指示(”conflicting” は「対立している」「食い違っている」の意味で、仕事や人間関係の話によく出る)
- technically: 建前上は/厳密に言えば(話のニュアンスを柔らかくする副詞。「実質とは違うけど…」と前置きするのによく使う)
- on paper: 書類上では/建前としては(実際と名目が違うときによく使われる比喩的表現)
- run the show: 実質的に仕切る/実権を握る(”run” は「走る」という意味が基本だが、英語では「動かす」「運営する」という意味でもよく使われる。”run the show” は、show(イベントや進行する何か)を動かしている=全体を仕切っているという比喩表現で、「表向きの肩書きに関係なく、実際に動かしてるのは誰か?」という場面でよく使われる。”call the shots” に近いが、”run the show” の方が**「現場を回している人」「表に出てる指揮役」**というニュアンスが強め)
- behind the scenes: 裏で/表に出ずに(舞台裏を表すフレーズから転じて、目立たないところで物事を動かしている様子)
- that sounds like her: それ、彼女っぽいね(”sound like 人” で「〜らしい」「〜にありがち」という口語表現)
- doesn’t wait around for approval: 承認を待たずに動く(”wait around” は「ただ待つ」「なんとなく待機する」といった意味。”around” は本来「周囲・まわり」を表すが、”wait around” のように使うと、「特に何もせずにその場をうろうろしている」=「はっきりした目的もなく、指示や変化を待ちながら、時間を潰している」ようなニュアンスになる。ここでは「承認(approval)が出るのを待って何もしない」のではなく、「自分で判断して動ける人」という積極的な姿勢を表現している)
- make things happen: 物事を実行に移す/動かす(行動力がある人を表現するときによく使われる決まり文句)