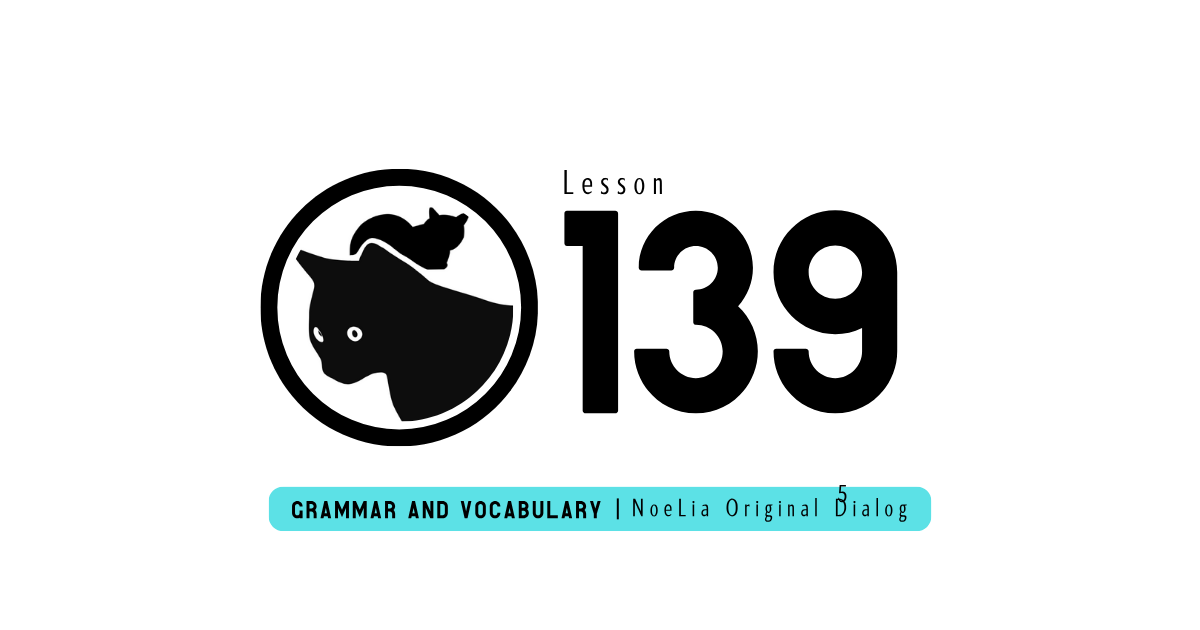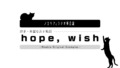GRAMMAR AND VOCABULARY(ノエリア オリジナル スクリプト)
下記では、本日の「Grammar and Vocabulary」の学習テーマに基づいた例題とその会話例を掲載しています。
学習内容が実際の会話でどのように活用できるかを具体的にイメージできるよう工夫されており、繰り返し練習することで日常生活でも無理なく使える英語表現を身につけることができます。
また、この素材はリスニングやディクテーション、スピーキングのトレーニングにも最適です。ぜひ学習の定着に役立ててください!
NoeLia Extra Examples|音読・暗唱のすすめ
音読・暗唱のすすめ
What did you think of today’s lecture?
引用:「NHKラジオ英会話 2025年10月号」 – 講師:大西泰斗(東洋学園大学教授) – (NHK出版:2025年)
あなたは今日の講義をどう思いましたか?
How did it go with your job interview?
日本語訳: 面接、どうだった?
解説: 「How did it go with ~?」は、出来事の結果や印象を尋ねるときの定番フレーズです。「How did it go?」だけでも通じますが、「with + 話題」をつけると、話の対象が明確になって自然です。たとえば「How did it go with your presentation?(プレゼンはどうだった?)」や「How did it go with your parents?(ご両親とはどうだった?)」のように幅広く使えます。音読でテンポよく口になじませると、会話でとっさに出せる便利な表現になります。
A: Hey, you finally called! I’ve been dying to know—how did it go with your job interview?
B: Oh, that. It went… surprisingly well, I think. They asked some tough questions, though.
A: That’s a good sign. It means they were actually interested in you.
B: Yeah, maybe. I just hope I didn’t talk too much about my old company.
A: やっと電話くれた!ずっと気になってたの、面接どうだった?
B: ああ、あれね。意外と良かったと思うよ。ただ、結構難しい質問もされたけど。
A: それっていい兆候じゃない?興味持たれてたってことだよ。
B: まあね。前の会社の話をしすぎてなきゃいいけど。
- I’ve been dying to know: ずっと知りたくてたまらなかった(”be dying to ~” は「~したくて仕方ない」という強い気持ちを表す口語表現)
- Oh, that.: ああ、そのことね。(会話でよく使う軽い導入表現。相手の話題を思い出したときの反応)
- surprisingly well: 意外と良く(“surprisingly” は「驚くほど」「思ったよりも」。結果が予想を上回ったニュアンス)
- tough questions: 難しい質問(“tough” は「固い」から転じて「厳しい・難しい」の意味。人にも物事にも使える便利形容詞)
- That’s a good sign.: それはいい兆候だね。(直訳すると「それはいいサインだね」だが、英語では“sign”が「兆し」「手がかり」「前触れ」の意味でよく使われる。日本語の「サイン」とは少し違い、良い/悪い流れの「気配」や「証拠」を表す自然な言い方)
- It means ~.: つまり~ということだよ(相手の発言を受けて理由づけや解釈を伝えるときの便利な構文)
- I just hope ~.: ~だといいなあ(“just” は気持ちをやわらげる副詞で、「ほんの少し願っている」ニュアンスを出す)
- old company: 前の会社(職場や組織を表すときの自然な言い方。“my previous company” よりカジュアル)
What did you make of the ending of that movie?
日本語訳: あの映画の結末、どう感じた?
解説: この表現は、相手の率直な感想や考えをもう少し深く聞きたいときに使います。「What did you think of~?」が一般的な「どう思った?」なら、「What did you make of~?」は“どう受け取った?” “どう解釈した?”というニュアンスを持つ、より知的で落ち着いた言い方です。動詞 make of には「〜を理解する・判断する」という意味があり、映画・本・スピーチなど考え方に個人差が出る話題で自然に使われます。
A: You’ve been quiet since we left the theater. Didn’t expect that from you.
B: I’m just thinking. That ending threw me off a bit — I wasn’t ready for it.
A: Yeah, I know what you mean. Still, what did you make of the ending of that movie?
B: I think it was brilliant, actually. Painful, but kind of necessary for the story to feel real.
A: 映画館出てからずっと静かだね。君がそんなに黙るなんて珍しい。
B: 考えてただけ。あの結末、ちょっと衝撃的すぎてさ。心の準備できてなかった。
A: うん、分かるよ。でもさ、あの映画の結末、どう感じた?
B: 実はすごく良かったと思う。痛みはあるけど、あのリアリティには必要な終わり方だった。
- quiet: 静かな(ここでは「黙っている」「話さないでいる」という意味で使われる。人の状態を表すときは「無言の」というニュアンス)
- Didn’t expect that from you.: 君がそんなふうになるとは思わなかった(”expect” は「予想する」。”from you” をつけることで「君らしくない」という軽い驚きや意外さを表すネイティブ的な言い方)
- I’m just thinking.: ちょっと考えてただけ(”just” が入ることで「深刻じゃない」「今は考えてるだけ」という柔らかいトーンになる。口語では非常に自然)
- threw me off: 面食らった/不意を突かれた(”throw off” は「投げ飛ばす」から転じて「調子を狂わせる」「戸惑わせる」の意味。感情的に「うろたえた」ときに使われる比喩的表現)
- I wasn’t ready for it.: 心の準備ができてなかった(”be ready for ~” は「~に備える」「~を受け入れる心構えがある」。ここでは感情的に“想定外だった”という意味で使われている)
- brilliant: 素晴らしい/見事な(直訳の「輝く」から転じて「才能が光る」「優れている」という比喩的な褒め言葉。映画・アイデア・人の発言などに使う)
- Painful, but kind of necessary: 辛いけど、ある意味必要だった(”painful” は「痛みのある」「胸が痛む」。“kind of” は「ちょっと」「ある意味」で口語的にトーンを和らげる)
- for the story to feel real: 物語が本物らしく感じられるために(”for ~ to …” は目的を表す不定詞構文。「~するために」。”feel real” は「リアルに感じる」という自然な英語の感覚)
NoeLia Extra Examples|空所ハンドリング2
空所ハンドリング2
What do you think he found there?
引用:「NHKラジオ英会話 2025年10月号」 – 講師:大西泰斗(東洋学園大学教授) – (NHK出版:2025年)
彼はそこで何を見つけたとあなたは思いますか?
Who do you suppose she meant by “an old friend”?
日本語訳: 彼女の言ってた “昔の友達” って誰のことだと思う?
解説: この文では、「mean … by ~」の「…」の部分が空所になっており、wh語「who」がその位置を補っています。つまり「彼女が“昔の友達”と言ったとき、それは誰を指しているの?」という情報の欠落をwhoが埋めているわけです。「mean … by ~」は「~で…を指す/言いたいのは…」という自然な言い方で、会話や噂話の文脈でよく使われます。
A: Emily seemed a little off tonight, didn’t she?
B: Yeah, especially when that photo from college came up.
A: Yeah… I noticed that too. So, who do you suppose she meant by “an old friend”?
B: Honestly, I think she was referring to Chris. You saw how quiet he got right after that.
A: 今日、エミリーちょっと様子おかしくなかった?
B: ああ、特に大学時代の写真が出てきたときね。
A: うん、私もそれ気づいた。でさ、「昔の友達」って誰のことだと思う?
B: 正直、クリスのことだと思う。あのあと彼、急に黙り込んでたの見たでしょ。
- seem off: 様子がおかしい(“off” は「いつもと違う」「調子が悪い」という意味で、人の雰囲気や態度に使われるネイティブ的な言い方)
- photo from college: 大学時代の写真(“from” は「〜の時代・起点」の意味で、期間や背景を表すときにも自然に使われる)
- came up: 話題に上がる/出てくる(“come up” は「出てくる」「話題にのぼる」「思い出される」など会話で非常に頻出のフレーズ動詞)
- Yeah… I noticed that too.: うん…私もそれ気づいた(“notice” は「気づく」だが、“see” よりも意識的・観察的なニュアンス。「あ、わかった」より「見抜いた」感じ)
- refer to ~: ~を指す/言及する(“refer” は「再び(re-)言う(fer)」が語源。「~のことを言う/~に触れる」という意味で使う)
- You saw how ~: ~だったの見たでしょ(“you saw how + 文” は「~だったの気づいたでしょ」という会話的な確認の言い回し)
- quiet: 静かな(人に対して使うと「黙っている」「無口な」というニュアンスになる。感情を抑えている印象も含む)
- right after that: その直後に(“right” はここでは「すぐ」「ぴったり」の意味を強調していて、時の近さを自然に表す)
I’m not sure who I should reach out to about this issue.
日本語訳: この件、誰に相談すればいいのか分からなくて。
解説: この文では、wh語「who」が前置詞「to」の目的語位置を補っています。つまり「誰に連絡すればいいのか」という空所を「who」が埋めている形です。「reach out to someone」は「〜に連絡する・相談する」という口語的な表現で、ビジネスでも日常会話でも使われます。「I’m not sure」は「よく分からない」「はっきりしない」という柔らかい言い回しです。
A: I’m stuck on this project report—the totals don’t line up with last quarter, and I can’t see why.
B: Hmm, that’s frustrating. You’ve checked the formulas already, right?
A: Yeah, everything looks fine on my end, but something still feels off. I’m not sure who I should reach out to about this issue.
B: Ping Daniel—he built the original format. He’ll spot what’s off in a second.
A: このプロジェクト報告書で行き詰まってて。合計が前期と合わないんだ、理由が見えなくて。
B: うーん、それは厄介だね。数式はもう確認した?
A: うん、こっちでは問題なさそうなんだけど、なんかおかしい気がして。この件、誰に相談すればいいのか分からなくて。
B: ダニエルに連絡して。元のフォーマット作った人だし、すぐにズレに気づくはず。
- be stuck on: 行き詰まっている(“stuck” は「動けない」状態を表し、問題や作業が進まないときによく使われる。物理的に“stuck in traffic(渋滞にはまって)”のようにも使える)
- line up with: ~と一致する/合う(“line up” は「列に並ぶ」「揃う」という基本の動作から、「位置や形がそろう=矛盾しない」というイメージが派生している。“with”を伴うことで「〜と方向がそろう」「〜と整合する」という意味になり、数字や意見などが一致する場面で自然に使われる)
- can’t see why: なぜ〜かわからない(直訳は「なぜかを見ることができない」だが、「理由が分からない」という自然な意味で使われる口語表現)
- that’s frustrating: それはイライラするね/困るね(共感や同情を込めたリアクション。日常会話で相手の気持ちに寄り添う定番の言い回し)
- check the formulas: 数式を確認する(“check”は「確認する」「調べる」の基本動詞。“formula”は「公式」「数式」を意味し、語源はラテン語の“forma(形・形式)”。そこから「決まった手順」「一定の形」を表すようになり、Excelなどでは「決まった形の計算式」という意味になる。また“Formula 1(F1)”の“formula”も同じ語で、「規定(レギュレーション)に基づいた」レースを指す。つまり「定められた形に沿っているか確認する」というイメージの言葉。)
- on my end: 自分の側では/こちらの環境では(“end”は「端」「側」という意味。ビジネスメールなどでも“Everything’s fine on my end.”のようによく使われる)
- something feels off: なんかおかしい感じがする(“off”は「ずれている」「いつもと違う」という感覚的なズレを表す口語表現。ネイティブが非常によく使う)
- ping someone: (人)に軽く連絡する(チャットやメッセージなどカジュアルな手段で連絡を取るときに使う。IT業界発祥のスラング的表現)
- spot what’s off: おかしいところを見抜く(“spot”は「見つける」「見抜く」。“off”は「ズレている」「正常でない」。直訳すると「ズレている部分を見つける」で、的確に違和感を見抜くという意味になる)