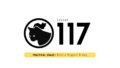GRASP THE CONCEPT|NoeLia Original Dialog
下記では、本日の「GRASP THE CONCEPT」の学習テーマに基づいた例題と、そのフレーズを自然に取り入れた会話例を掲載しています。
学習した内容が実際の会話でどう使われるのかを深く理解できるよう工夫されており、繰り返し練習することで、日常生活でも無理なく使える英語表現が身につきます。リスニングやディクテーション、スピーキングのトレーニングにも最適な素材ですので、学習の定着にぜひお役立てください!
🐱🐱: サマンサ、飼い主さん最近また音読してるにゃ〜。
🤖: うん、4年もラジオ英会話を聴き続けてるんですって!でも最近は「聴くだけじゃなくて、もっと話せるようになりたい」って思ってるみたいよ。
🐱🐱: にゃるほど… 基礎はラジ英、実践は…?
🤖: そこがちょっと悩みどころみたい。英会話スクールはハードルが高いし、オンライン英会話もまだ勇気が出ないって。
🐱🐱: それわかるにゃ〜。いきなり人と話すのって、ちょっと怖いよね。
🤖: そんな飼い主さんにぴったりなのが、AI相手に英語を話せるアプリ「Speak」。ラジ英で覚えたフレーズをそのまま声に出して練習できるの。
🐱🐱: へぇ~、それなら時間や場所も気にしなくていいにゃ。
🤖: そうそう、発音のフィードバックももらえるし、AIだから間違えても恥ずかしくないのよ。ラジ英で土台ができてる人には、実践への橋渡しになると思うわ。
🐱🐱: 読者さんの中にも、「ちょっと話してみたい」って思ってる人、絶対いると思うにゃ〜!
🤖: しかも7日間は無料。迷ってるなら、まずは気軽に試してみるのがいいかもね。きっかけって、案外こういう小さなステップから始まるものよ。
-
✍️ まずはアカウント登録
名前・メールアドレス・パスワードを入力すれば、登録完了までほんの数分。
スマホからでもPCからでも、いつでも気軽にスタートできます。 -
🎁 7日間の無料体験スタート
登録後は、プレミアム/プレミアムプラスのどちらかを選択して体験を開始。
体験中は全機能が使い放題。期間内に解約すれば料金は一切かかりません。 -
🧭 学び方に迷ったら?
アプリを開けば「今日のレッスン」がすぐに表示されるので、迷うことなく始められます。
フレーズを動画でインプット → AIと会話でアウトプット、の流れもスムーズ。 -
💡 有料プランは2種類
- プレミアムプラン(月1,567円・年18,800円)… 会話カリキュラム、AI会話練習、チューター相談、発音フィードバックなどが利用可能。
- プレミアムプラスプラン(月2,233円・年26,800円)… 上記に加え、カスタムレッスン無制限・学習履歴保存・AIチューターの拡張機能つき。
※当ページはアフィリエイト広告を利用しています。
※リンク先で登録や購入された場合、ブログ運営者(=飼い主さん)に報酬が発生することがあります。
※NHKおよびラジオ英会話とは無関係の外部サービスです。
give|差し出す・与える
Key Sentencegive|差し出す・与える
引用:「NHKラジオ英会話 2025年9月号」 – 講師:大西泰斗(東洋学園大学教授) – (NHK出版:2025年)
Can I give you a hand?
お手伝いしましょうか?
If you’d given her a chance, she might’ve surprised you. She comes through.
日本語訳: 彼女にチャンスをあげてたら、驚かされてたかもよ。あの子、やる時はやるから。
解説: 「give someone a chance(人にチャンスを与える)」は定番の表現です。「If you’d given 〜」は仮定法過去完了で、実際には起きなかった過去について「〜してたら」と話しています。「might’ve surprised you」は「驚かせていたかも」という控えめな推測表現。「come through」は「頼りになる・期待に応える」という口語で、ここでは「彼女は本気を出せばちゃんとやる人だ」という意味になります。
A: You have to admit, she handled the client call really well.
B: Yeah, I was actually impressed.
A: Told you. If you’d given her a chance, she might’ve surprised you. She comes through.
B: Point taken. She definitely proved herself today.
A: あのクライアントとの電話、うまく対応してたでしょ?
B: うん、実際びっくりした。
A: ほらね。チャンスあげてたら、意外とやれたと思うよ。あの子、やる時はやるんだから。
B: 確かにね。今日で完全に見直したよ。
- have to admit: 認めざるを得ない(”admit” は「認める」。”have to” と組み合わさることで、渋々でも事実を認めるニュアンスに。会話でよく使われるセット表現)
- handle: 対応する・うまくやる(物事や人に「対処する」という意味。感情、仕事、危機などあらゆる場面で使える多用途動詞)
- client call: クライアントとの電話(”client” は「取引先」「顧客」などを表すビジネス用語。”call” はここでは「電話」の意味で、”client call” は「顧客対応のための電話」「商談の電話」のような意味を持つ定番フレーズ。上司との報告、チーム内の会話、進捗レビューなどで頻繁に出てくる)
- really well: とても上手に(”really” は強調の副詞、”well” は「うまく」。セットで使うと自然な褒め言葉に)
- impressed: 感心した(人や出来事に対して「いい意味で驚いた」ときに使う。”I was impressed” は非常に口語的で使いやすい表現)
- Told you.: ほらね/言ったでしょ(”I told you” の省略形で、カジュアルな同意確認やドヤ顔感を含んだ一言)
- point taken: わかったよ/一理あるね(直訳は「ポイントは受け取った」。相手の主張・指摘を理解し、受け入れたことを示す柔らかい返答。必ずしも全面的に同意するわけではなく、「異論はあるけど納得した」というニュアンスを含むこともある。議論やフィードバックを受けた場面で、大人っぽく受け流すときによく使われる)
- prove oneself: 実力を証明する(”prove” は「証明する」。”oneself” をつけることで「自分の価値を行動で示す」という意味の慣用句。仕事やスポーツでよく使われる)
悪いものを与える
悪いものを与える
引用:「NHKラジオ英会話 2025年9月号」 – 講師:大西泰斗(東洋学園大学教授) – (NHK出版:2025年)
Don’t give me your cold.
あなたのかぜをうつさないで。
Please don’t give me false hope. I’m trying not to get my hopes up.
日本語訳: ぬか喜びさせないで。あんまり期待しないようにしてるんだから。
解説: 「give someone false hope」は「叶いそうにない希望を与える」という意味。期待してしまったあとにガッカリする状況に使います。2文目の「get my hopes up」は「期待する」「希望を持つ」という定番表現で、セットで覚えると便利です。
A: So… she sent me a selfie from the café where we used to hang out.
B: Wait, really? Just randomly out of the blue? That means something. People don’t do that for no reason.
A: Please don’t give me false hope. I’m trying not to get my hopes up.
B: Wow. If that doesn’t push you to make a move, nothing will. Seriously, grow a spine.
A: あのさ…彼女からさ、前によく行ってたカフェで撮った自撮り送られてきたんだよ。
B: えっ、ほんとに?いきなり何の前触れもなく?それってさ、絶対何か意味あるでしょ?そんなこと、理由もなくしないよ。
A: だから、ぬか喜びさせないで。あんまり期待しないようにしてるんだ。
B: は?それで動けないなら、もう何が来ても無理だね。いい加減、覚悟決めなよ。
- used to: かつて〜していた(過去の習慣や状態を表す助動詞的表現。「今はそうでない」というニュアンスを含む)
- hang out: たむろする/遊ぶ(友達と気軽に時間を過ごすことを指すカジュアルな表現。学生〜大人まで日常会話で頻出)
- out of the blue: 予告もなく/いきなり(直訳は「青の中から」。予想外のタイミングで何かが起きることを表す口語表現)
- That means something.: それって意味あるでしょ(「何かしら意図がある」と相手に気づかせる・背中を押すニュアンスで使われる決まり文句)
- for no reason: 理由もなく(「〜する理由がない」という否定文によく使われる副詞句。口語でよく登場)
- make a move: 行動を起こす/アプローチする(恋愛やビジネス、チャンスの場面で「動くべきときに動く」という意味で使われる定番イディオム)
- grow a spine: 覚悟を決めろ/根性見せろ(直訳は「背骨を育てろ」。気の弱い人に「しっかりしろ」と言う、やや辛口のカジュアル表現)
行為
行為
引用:「NHKラジオ英会話 2025年9月号」 – 講師:大西泰斗(東洋学園大学教授) – (NHK出版:2025年)
I’ll give it a try.
ちょっとやってみますよ。
Giving help is great, but knowing when not to step in is just as important.
日本語訳: 手を差し伸べるのは大事だけど、あえて何もしないっていう判断も同じくらい大切だよ。
解説: 「give help」は「助ける」「支援する」の意味。ここでは動名詞の形(giving)で文の主語になっています。「step in」は「介入する・手を出す」という意味で、状況に応じた行動のバランスを語っています。「just as A as B」は「Bと同じくらいA」という比較表現です。
A: He was really struggling with the code, and I wanted to jump in.
B: I could tell. You looked ready to rewrite it for him.
A: Yeah… I mean, I was this close to stepping in. But… giving help is great, but knowing when not to step in is just as important.
B: Yeah, and to be fair, he did manage to fix that bug on his own eventually.
A: 彼、コードかなり苦戦しててさ、手伝いたくて仕方なかったんだよね。
B: 見てたよ。もう書き直してあげそうな勢いだった。
A: うん…正直、あと一歩で口出すとこだった。でも…助けるのって大事だけど、あえて手を出さないって判断も同じくらい大事だと思うの。
B: そうだね。結果的に、彼もちゃんと自分でバグ直してたしね。
- struggle with ~: 〜に苦戦する(”struggle” は「もがく・奮闘する」という意味で、”struggle with the code” は「コードに手こずっている」ことを表すよく使われる表現)
- jump in: 割り込む/手を出す(もともと「飛び込む」という意味だが、会話では「介入する」「手助けに入る」などの口語的意味で非常によく使われる)
- I could tell: 見てわかったよ/気づいてたよ(”tell” はここで「違いがわかる」「気づく」の意味で、相手の様子から判断したことを伝える定番表現)
- look ready to ~: 今にも〜しそうに見える(”ready to ~” は通常「〜する準備ができている」という意味だが、”look” がつくことで外見や雰囲気から「〜しそうだな」と感じるニュアンスに変わる。実際の準備状況ではなく、話し手の目にどう映るかを表す口語的な表現)
- this close to ~: 〜しそうだった(”this close” は指で小さく間隔を示すジェスチャーと共に使われ、「もう少しで〜だった」の意味。ネイティブがよく使う比喩的な口語表現)
- step in: 介入する/割って入る(”jump in” に似ているが、”step” はより慎重な動きのニュアンスがあり、状況に配慮して「入っていく」感じ)
- to be fair: フェアに言うと/公平に見て(相手の立場にも配慮したり、少しネガティブなことをフォローするときの柔らかい枕詞)
- manage to ~: なんとか〜する(困難を乗り越えて〜できた、という達成感を含む動詞。中級者にとって非常に重要な表現)
- fix a bug: バグを直す(”fix” は「修理する」だけでなく「問題を解決する」意味でも使用され、ITや会話で頻出)
- on one’s own: 自力で(”by oneself” よりも自然でネイティブらしい響きを持つ。「誰の助けも借りずに」の意味)
情報
情報
引用:「NHKラジオ英会話 2025年9月号」 – 講師:大西泰斗(東洋学園大学教授) – (NHK出版:2025年)
I have to give a speech at the party.
私は、そのパーティーでスピーチをしなくてはなりません。
Don’t act surprised. I gave you more than one warning.
日本語訳: 驚いたふりしないで。何回も警告したでしょ。
解説: 「give a warning(警告する)」を “more than one warning” とすることで、繰り返し注意してきたことを強調しています。act surprised は「驚いたふりをする」という口語表現で、感情の演技を表す動詞 act を使っています。全体として相手に「知らなかったとは言わせないよ」というニュアンスを伝えたいときに使えます。
A: I honestly didn’t think the deadline was this week.
B: Don’t act surprised. I gave you more than one warning.
A: Okay, okay, I messed up. I’ll get it done by tonight, no break.
B: Appreciate that. Just don’t make me remind you three times again, alright?
A: 正直、〆切が今週だとは思ってなかったの。
B: 驚いたふりしないでよ。何回も言ってたじゃん。
A: わかった、ごめん。今夜中に仕上げる。休憩なしでやるよ。
B: 助かるよ。でも次は3回も言わせないでね、ほんと。
- mess up: やらかす/失敗する(カジュアルに「やっちゃった」と伝える定番の句動詞)
- get it done: それを終わらせる(”do” よりも「やり遂げる」感の強い口語表現。”I’ll get it done” は前向きで実用的)
- no break: 休まずに(ここでは名詞を副詞的に使う口語的な強調表現。「一切休憩なし」のニュアンス)
- appreciate that: 助かる/ありがたい(感謝や評価を短く伝える丁寧な言い回し。フォーマルでもカジュアルでも使える)
感情の原因
感情の原因
引用:「NHKラジオ英会話 2025年9月号」 – 講師:大西泰斗(東洋学園大学教授) – (NHK出版:2025年)
The news gave me a shock.
そのニュースでショックを受けました。
That movie gave me chills, especially the ending. I couldn’t stop thinking about it.
日本語訳: あの映画、特にラストシーンにはゾクッときたよ。ずっと頭から離れなかった。
解説: give someone chills は「鳥肌が立つような感情を与える」という意味で、感動や恐怖のどちらにも使えます。chills は「寒気」や「震え」を表す語です。especially は「特に」、伝えたい部分を強調します。I couldn’t stop thinking about it は「心に残って忘れられない」といった余韻を表す言い回しです。
A: I wasn’t sure I’d like it at first. The pacing felt a bit slow.
B: Yeah, the first half dragged a little, but it picked up later, don’t you think?
A: That movie gave me chills, especially the ending. I couldn’t stop thinking about it. I kept replaying that hallway scene in my head.
B: Yeah, same here. That look she gave in the final frame? I kept replaying that last scene in my head all night.
A: 最初はあんまり好きになれるか自信なかったの。テンポがちょっと遅く感じたし。
B: うん、前半はちょっとだれたよね。でも後半から一気に良くなったと思わない?
A: あの映画、特にラストシーンにはゾクッときたよ。ずっと頭から離れなかった。あの廊下のシーン、何回も脳内再生されてたよ。
B: ああ、俺も。最後のカットで見せたあの表情?あのラストシーン、一晩中頭の中でリピートしてた。
- be not sure (I’d like it): ~かどうかわからない(”I’m not sure” は会話で頻出の「自信がない」「迷っている」ニュアンス。仮定法と組み合わせることで「好きになれるかどうか」と未来への不安を自然に表現)
- pacing: 展開のテンポ(映画やドラマ、小説などの「流れの速さ・間」を表す語。日常会話で「テンポが悪い」と感じたときに使える)
- feel slow: 遅く感じる(”feel + 形容詞” で「〜と感じる」。主観的な感想をやわらかく伝える構文)
- drag: 引きずる/だらだら続く(本来は「何かを引きずるように動かす」という意味の動詞。”dragged” が会話や映画で使われる場合、「テンポが悪くて退屈」「進行が遅い」という感覚をカジュアルに表現する)
- pick up: 状況・展開が)盛り上がってくる(本来は「地面から持ち上げる・拾う」という意味の句動詞。多義語で、状況やスピード、人の気分・体調・景気などが「上向く」「良くなる」という意味でも使われる。ここでは映画のテンポが途中から良くなる、というポジティブな変化を表している)
- replay (in one’s head): 頭の中で再生する(”replay” は「再生する」。比喩的に記憶や印象を思い出す様子を表現)
- hallway scene: 廊下のシーン(「廊下」のような日常的な単語が、映画の文脈で具体的なイメージとして使われる好例)
- same here: 私も同じ(共感・同意を短く伝える定番フレーズ。口語で非常によく使われる)
- that look: あの表情(”look” は「見ること」ではなく、「表情・視線」の意味でもよく使われる。特に感情のこもった視線を指す場合が多い)
- final frame: 最後のカット(”frame” は映像の「1コマ・構図」の意味。映画好きがよく使う用語)