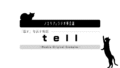GRAMMAR AND VOCABULARY(ノエリア オリジナル スクリプト)
下記では、本日の「Grammar and Vocabulary」の学習テーマに基づいた例題とその会話例を掲載しています。
学習内容が実際の会話でどのように活用できるかを具体的にイメージできるよう工夫されており、繰り返し練習することで日常生活でも無理なく使える英語表現を身につけることができます。
また、この素材はリスニングやディクテーション、スピーキングのトレーニングにも最適です。ぜひ学習の定着に役立ててください!
NoeLia Extra Examples|that big of a deal
that big of a deal
It’s not that big of a deal.
引用:「NHKラジオ英会話 2025年11月号」 – 講師:大西泰斗(東洋学園大学教授) – (NHK出版:2025年)
それは、そんなに大げさなことではありません。
Is it really that big of a problem, or are you overthinking it?
日本語訳: それって本当にそんなに大きな問題?ちょっと考えすぎじゃない?
解説: “that big of a problem”の部分では、a big problem(大きな問題)という名詞句から、形容詞bigがthatを伴って前に抜き出されています。thatが加わることで「そこまで大きな」という強調のニュアンスが生まれます。このように“that+形容詞+of a〜”の形は、程度を強く感じるときに使われます。また、“overthink”は「考えすぎる」という意味の口語的な動詞で、相手の心配をやわらかくたしなめる自然な言い方です。
A: I’ve been thinking — maybe we should change the entire intro. It doesn’t sound engaging enough.
B: Change the entire intro? That’s a lot of work.
A: Yeah, but if the audience doesn’t connect right away, we’ll lose them.
B: Is it really that big of a problem, or are you overthinking it? The feedback from the last run-through was great.
A: ちょっと考えてたんだけど、最初の導入、全部変えた方がいい気がするの。インパクトが足りない気がして。
B: 導入全部?けっこう大がかりだね。
A: うん、でも最初でつかめないと流れも崩れるし。
B: 本当にそんな大きな問題かな?ちょっと考えすぎじゃない?前回のフィードバックも良かったじゃん。
- I’ve been thinking: ちょっと考えてたんだけど(“have been + ing”で「ここ最近ずっと考えていた」という現在完了進行形。柔らかく話を切り出す定番フレーズで、議題を出す前の自然な導入に使われる)
- change the entire intro: 導入部分を全部変える(“entire”は「全体の/すべての」。部分的ではなく「丸ごと変える」ニュアンス。“intro”は“introduction”のカジュアル短縮形で、プレゼンや文章などの冒頭部分を指す)
- engaging: 引き込まれるような/魅力的な(“engage”の形容詞形。“engage”のコアイメージは「関わりを持つ・かみ合う」。もともとは「歯車がかみ合う」ように「相手とつながる」「注意や感情を引き込む」動きを表す。単に「面白い」よりも「相手の注意を引きつけ、巻き込む」ニュアンス。特にビジネスやプレゼンの文脈で「聴衆を惹きつける」意味で頻出)
- That’s a lot of work: それは大変だね(直訳は「それはたくさんの仕事」。負担が大きいという意味で「手間がかかる」「面倒だ」という日常的な感想を自然に伝える表現)
- connect: 心が通じる/共感する(ここでは“audience connects”=「聴衆が共感する」。人と人、または人と内容が“つながる”感覚を表す。単なる通信的な「つなぐ」ではなく「感情的に響く」意味)
- right away: すぐに(即座に・間を置かずに、という口語的副詞。“immediately”よりも日常的で柔らかい)
- lose them: 聴衆の関心を失う(“lose”は「失う」。“them”は“the audience”を指す。英語では「関心・注意を失う」も“lose”で自然に表せる。“We’ll lose them.”=「聞く気をなくされる」)
- run-through: 通し練習/リハーサル(“run through”=「ざっと通してやる」から派生。プレゼンや舞台などで一通り流れを確認する軽いリハーサルを指す口語)
- feedback: フィードバック/意見(評価や感想を表す定番名詞。職場・教育・クリエイティブな場面で非常に頻出。“get/give feedback”で「意見をもらう/伝える」)
That’s too nice of a restaurant for a first date.
日本語訳: 初デートにしては、ちょっといいお店すぎない?
解説: “too nice of a restaurant”は、a nice restaurant(いいお店)から形容詞niceを前に抜き出し、“too”を添えることで「〜するには〜すぎる」という意味を作っています。ここでは“for a first date”が基準を示し、「初デートとしてはちょっと高級すぎる」という軽いからかいのニュアンスになります。この“too+形容詞+of a〜”の形も、that構文と同様に、話し手の感覚や評価を強調するときによく使われます。
A: Wait, you said he made a reservation at Le Jardin? That’s too nice of a restaurant for a first date.
B: I know, right? I was thinking maybe a café or something casual, but he insisted.
A: Wow, he’s really going all out. Guess he’s trying to make a good impression.
B: Yeah, but now I feel like I have to dress up way more than I planned.
A: え、ル・ジャルダンに予約したって?初デートにしては、ちょっといいお店すぎない?
B: だよね?ほんとはカフェとかもっと気軽なとこでよかったのに、彼がどうしてもって。
A: うわ、それ本気モードじゃん。いい印象残したいんだろうね。
B: そうなの。でもおかげで、想定以上にドレスアップしなきゃいけなくなっちゃった。
- made a reservation: 予約した(“make a reservation”は「予約を取る」。“book”と同じ意味だが、“make a reservation”の方がややフォーマルで丁寧な響き)
- I know, right?: でしょ?(強い同意や共感を表す口語表現。“I know.”だけよりも共感の温度が高く、親しい間柄でよく使う)
- something casual: 気軽な感じのもの(“casual”は服装だけでなく「フォーマルでない」「気取らない」場や雰囲気にも使われる。食事・会話・場所などを形容できる汎用的な語)
- he insisted: 彼がどうしてもって(“insist”は「強く主張する」「譲らない」。“he insisted”だけで「彼が強く言った/押し切った」という含みが伝わる)
- going all out: 全力を尽くす/とことん頑張る(“all out”は「全力で」「出し惜しみなく」の意味。恋愛・仕事・スポーツなど幅広い場面で使えるカジュアルな口語表現)
- make a good impression: いい印象を与える(“impression”は「印象」。“make”と組み合わせて「印象を作る」「与える」になる定番表現。“first impression”で「第一印象」)
- dress up: おしゃれをする/正装する(“dress”単体は「服を着る」だが、“up”が加わることで「普段よりもきちんとした格好をする」ニュアンスになる)
- way more than: ~よりずっと(“way”は「道」ではなく「ずっと・かなり」という強調の副詞。“much more than”よりも口語的で勢いがある)
NoeLia Extra Examples|助動詞+現在完了形
助動詞+現在完了形
They could have discussed it with us first.
引用:「NHKラジオ英会話 2025年11月号」 – 講師:大西泰斗(東洋学園大学教授) – (NHK出版:2025年)
彼らは、まず私たちとそれを議論することもできたでしょうに。
I should’ve known better than to trust him again.
日本語訳: もう一度あいつを信じるなんて、バカだったよな。
解説: この文は「助動詞+現在完了形」で、過去の自分の判断を振り返る形です。“should have+過去分詞”で「〜すべきだったのに(しなかった)」という後悔を表します。“know better than to〜”は「〜するなんて軽率だった」という慣用句で、冷静に考えれば避けられた失敗を意味します。
A: Wait, you lent him money again? After everything he pulled last time?
B: Yeah, he said it was just for a few days. I wanted to give him the benefit of the doubt.
A: And let me guess—he disappeared again?
B: Exactly. I should’ve known better than to trust him again.
A: ちょっと待って、またあの人にお金貸したの?前回あんなことあったのに?
B: うん、「数日だけ」って言うからさ。もう一度だけ信じてみようと思ったんだ。
A: で、またいなくなったんでしょ?
B: その通り。もう一度あいつを信じるなんて、俺がバカだったよ。
- lend (someone) money: (人に)お金を貸す(“lend”は「貸す」、“borrow”は「借りる」。混同しやすいが、主体が“お金を出す側”なら“lend”を使う)
- after everything (someone) pulled: あの人が前にやらかしたことを考えたら(“pull”は「引っ張る」がコアイメージだが、ここではスラング的に「悪さをする」「ずるいことをする」の意味。“After everything he pulled”で「彼があんなことをしたのに」という皮肉を込めた言い方。──この“pull”がスラング化した背景には、“pull a stunt(とんでもないことをやらかす)”“pull a trick(ずるい手を使う)”“pull a fast one(人をだます)”といった表現の影響がある。つまり「何かを仕掛けて相手を出し抜く」「裏で手を引く」という比喩的な「引っ張る(=行動を起こす)」から転じて、“pull”単独でも「(よくないことを)やらかす・企む」という意味が生まれた)
- it was just for a few days: 数日だけのつもりだった(“just”は「ほんの」「たったの」と軽く言い訳するような口調を作る)
- give (someone) the benefit of the doubt: 相手を疑わずに信じてみる(直訳は「(疑わしい状況でも)相手に“疑いの利益”を与える」。つまり、証拠がはっきりしないときに「悪意がない」と信じる側に立つという意味で、相手の言葉を信じる姿勢を表す定番表現)
- let me guess: 当ててみようか(相手の言いそうなこと・予想できる展開を皮肉っぽく言うフレーズ。軽いあきれや察しのニュアンスを含む)
- disappear: 姿を消す/いなくなる(物理的に「消える」だけでなく、「連絡を絶つ」「消息を絶つ」という比喩的な意味でもよく使われる)
- Exactly.: その通り(相手の発言に完全に同意するときのカジュアルで強いリアクション)
She might’ve meant it as a joke, not an insult.
日本語訳: 彼女、冗談のつもりで言ったんじゃない?悪気はなかったと思うよ。
解説: “might have+過去分詞”は、過去の出来事に対して「〜だったのかもしれない」と推測する形。ここでは“meant it as〜”で「〜として言った」という意図を示しています。“insult”は「侮辱」の意味で、“not an insult”が否定することで柔らかく相手をかばう言い方になります。
A: I can’t believe what Mia said to you in front of everyone. That was so rude.
B: Yeah, it stung a bit, but honestly, I don’t think she meant to hurt me.
A: Really? You’re being way too nice about it.
B: She might’ve meant it as a joke, not an insult. I know her — she teases everyone the same way.
A: ミアがみんなの前で言ったこと、信じられない。あれ、ひどくない?
B: うん、ちょっと傷ついたけど、たぶん悪気はなかったと思う。
A: ほんと?君、優しすぎるよ。
B: 彼女、冗談のつもりで言ったんじゃない?悪意とかじゃなくて、あの人いつもあんな感じだし。
- rude: 失礼な/無礼な(単に「マナーが悪い」だけでなく、「思いやりがない」「無神経」という意味でも使われる)
- stung: (心が)チクッとした/傷ついた(“sting”はもともと「刺す」「痛みを与える」。ここでは比喩的に「心に刺さる」=精神的に痛い思いをするという意味)
- mean to (do): 〜するつもりである(ここでは“meant to hurt me”で「傷つけるつもりだった」という意図を指す。“mean”は「意図する」動詞として重要)
- hurt: 傷つける(物理的なケガにも、感情的なダメージにも使える多義語。“It hurt my feelings.”=気持ちが傷ついた、も定番)
- you’re being way too nice: あなた、優しすぎるよ(“be being”で「一時的に〜な状態にある」。“way too〜”は「かなり〜すぎる」と強調する口語)
- tease: からかう(もともとは「引っ張っていじめる」「いじって反応を楽しむ」という意味の動詞。相手の反応を面白がるニュアンスがあり、愛嬌のある軽いからかいから、悪意のあるいじりまで幅広く使える。ここでは“teases everyone the same way”で「みんなを同じようにからかう」)
- the same way: 同じように(行動や態度の一貫性を表す基本フレーズ。日常会話でも非常に頻出)